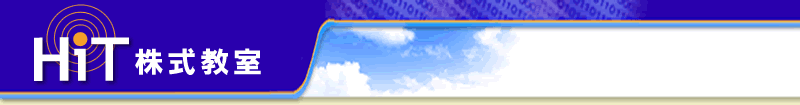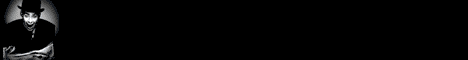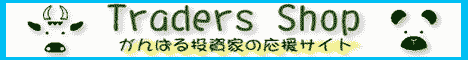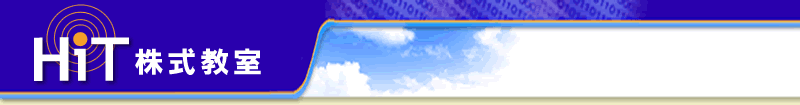
 (2).gif)
お知らせ:読者のみなさんで、「著者がどのような人物か詳しく知りたい。」「直接、話しが聞きたい。」など考えていらっしゃる方はお名前などをこのフォームから記入してメールをお願いします。
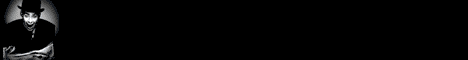
電話注文でもオンライン注文でも、どちらも可能で手数料が安い証券会社です。
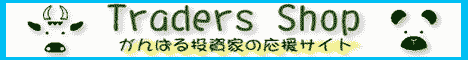
![hit_bana[1].gif](hit_bana[1].gif)
![sennin_bana[1].gif](sennin_bana[1].gif)
![cocktail_bana[1].gif](cocktail_bana[1].gif)
具体的な戦略や参考銘柄、テクニカル分析などは各メールマガジンをご購読下さい。
【お知らせ】Meネット証券タイアップ 「お試し版」無料配信キャンペーン
9月1日(月)から10月24日(金)の間、Meネット証券で新規に口座を開設されますと、口座開設後の翌週月曜日より当サイトの「HITメールマガジンお試し版」を無料配信致します。なお配信期間は、10月31日(金)までの限定となりますので、お早めにお申込み下さい。
2003年9月24日(水)
溝口財務官と黒田前財務官の差。
黒田氏から溝口氏に財務官が交代してから、初の為替介入で溝口氏は覆面介入を実行し、独自性を打ち出しました。ところが、9兆円以上も介入した結果は惨憺たるもので、介入資金は大幅な「含み損」となっています。それに比べて、黒田財務官の時代は介入はことごとく成功し、常勝介入といっても良いほどでした。この差は大きいものがありますが、その差は「市場に対する理解と実践の差」からきているようです。
まず、為替の介入について前財務官は「為替は完全に制御できないが、ファンダメンタルズから乖離し、行き過ぎたポイントで介入すれば効果がある」という基本のスタンスが明確であったと思います。それに対して、黒田財務官は「円高は介入で制御できる」と最初から決めてかかっているようなところがあります。市場軽視とも受け取れますし、いかにも官僚的な発言が気になります。
実践的な面で言えば、前財務官はエコノフィジックスの考え方で市場心理を数値的に分析し、効果的なポイントを探っていた合理性があったと感じましたが、溝口氏の場合は「115円以上の円高は許さない」と言ったような固定的な相場観に基づいた市場介入を中心に行っているように見えます。政策的に管理相場を強引に作ろうとしたとも受け取れます。固定的な相場観では想定した「壁」が崩れると大きくなる弊害が出ます。
この結果、外為特別会計に黒字を蓄積していった前財務官と10兆円近い介入で効果が出せない現財務官との差は歴然としています。まだ、在任期間が短いことが言い訳になりますが、新財務大臣と合わせて市場の信任を得ることは簡単ではないでしょう。
日経平均は輸出関連のハイテク株の寄与度が高い指数であり、当面ボラタイルな展開が避けられない情勢です。指数的には日経平均とTOPIXを使ったNT倍率によるインターマーケット・アービトラージ(インタマ)が面白いのですが、あまり個人向きではありません。もともと、このところTOPIXに比べて割安感のあった日経平均ですから、為替の一段の円高場面があれば買い場と見て良いのではないでしょうか。為替について実務的に信頼感は薄いものの、これ以上の円高は放置できないでしょう。
2003年9月22日(月)
過保護な為替管理政策の失敗。
国際的な批判がない間はMOFの円高を認めない姿勢によって投機的な動きを封じ込めることが出来ました。しかし、その国際世論の「壁」が崩れると急激に変動してしまう危うさがあり、今回は米国の意向の変化(?)で前提が崩れた結果、「世界で最も動かない通貨」であった円は投機筋のターゲットに変化したようです。
政治的な空白時期や祝日を選んで投機的な動きを強めたことは想像に難くありません。日本市場が休みであれば円高が仕掛けやすいでしょうし、介入政策に米国が批判的な姿勢に転じたのであればNY連銀に委託介入を依頼するのも気がひけるというものでしょう。
動かなかった相場が動き始めると大きくなるのは8月末の債券市場と同じです。円高もまだ止められないかもしれません。しかし、円を買うということは輸出主導で回復していた日本経済を弱めることですから、それ自体、自己矛盾を含んでいます。投機筋もどこかで矛先を収める必要があります。それにしても、債券市場を売り崩し株式を急騰させたかと思えば、円を急騰させ株式を急落させたりで、国際的な投機筋の為すがまま、良い様に動かされている印象です。
対抗策として、この円高は大幅減税を実施している米国の財政事情がありますから、本来なら、円高を止めるのは介入ではなく、日本も大幅な減税をすれば良いことになります。財政悪化に対して財政悪化で対抗すべきでしょう。同じ財政悪化でも、「円高不況を是正する公共事業の増加」という政策は危険です。世界が円を強い通貨と認めるなら、大幅な減税を実施し、円安政策で景気回復を図るチャンスです。その後に消費税引き上げを議論すれば良いのではないでしょうか。新内閣には介入ではなく政策で対抗して欲しいものです。
日経平均は11000円台への上昇がTOPIX型で行われただけに、225型は出遅れていた部分がありました。そこへ更に急激な円高でTOPIXに比べて一層割安感が出てきたことも事実です。日経平均はハイテク株指数の性格を持つだけに円相場は大きな変動要因で、かなりボラタイルな動きにならざるを得ませんが、TOPIXからの比較感からしても、為替相場が落ち着いた場合、戻りも早そうです。
2003年9月19日(金)
熱狂の中の冷静さ。
過熱感のある上昇相場ではありますが、割高と見られている銘柄が急落したり、週末には必ずといって良いほどポジション調整が入り、やや甘い引け方となるなど冷静な部分も見受けられます。今月初めの買いパニックの場面では強気一色でしたが、それ以降は冷静さを残しながら高値を形成するパターンを見せています。
そのあたりにITバブルの教訓が活きているとも言えそうですが、ピンポイントの売り場を探ることは難しくなります。市場に冷静さがある間は急騰場面につられて買わない限り大怪我をすることもないでしょう。利食いをした後に上昇する株を見て損をした気分になり、高値で買い直すようなことをすると、これまでの利益を飛ばすような悪循環に陥ります。
信用取引の場合、売りを規制しましたが、膨れる一方の買いは何の規制もされません。買い方は自分だけは高値で売り逃げられると信じて買いますが、結果としては、相場のピークと信用の買い残のピークは、ほとんどの場合、一致します。つまり、お金を借りて株を買った人が最も多くなったところがピークになる訳ですから、(どこが終点かは分かりませんが)逃げ遅れる人の方が売り逃げる人よりも圧倒的に多いという結果がいつの相場でも待っていることになります。強気が広まれば広まるほど「いつでも降りられる準備」をしながら多数派と付き合うことが必要でしょう。暴落は政府が管理する国ですが、高値は自分で管理する以外に方法がありません。
日経平均は今年のほとんどがそうであったように週末より週明けが高いという展開を予測しますが、実質中間決算末という特殊な週になるだけにその後の対応は難しくなりそうです。また、期末要因だけでなく、「ハイテク株指数」の性格を持つ日経平均は為替相場による影響が大きく、当局の介入目標とも考えられる115円の攻防がどうなるかも目が離せません。これまで9兆円も介入してきた当局が10兆円の大台乗せの介入に向かうのかどうか、ドルの流動性供給の問題と合わせて気になるところです。為替市場の影響が大きくなっている為に日経平均のボラティリティは更に上がりそうな気配です。
2003年9月18日(木)
必要悪の金利高。
今週は債券も株式も高いという不思議な光景が見られます。しかし、どちらかの市場に無理があり、もし、日本経済をまともな状態にしたいなら、債券安=金利高を容認する姿勢が必要でしょう。
日本経済がある程度まともな状態になれば金利は上がるべきで、銀行業などは金利が存在しないような低金利では業として成り立ちません。銀行は金利が低過ぎる状態では僅かの金利で大きな貸し倒れリスクを抱えるアンバランスな経営を続けざるを得ず、不良債権問題と常に同居するしかありません。「金融緩和=景気対策」という考え方も長く続けると弊害のほうが問題になってきたように感じます。
また、輸出企業にとっても経営を安定させる為に貿易相手国と金利差が有り過ぎると為替予約が取り辛く困ることになります。例えば、輸出企業が対ドルで120円で為替予約を先々まで取りたい場合を想定すると、1年先なら手取り115円といった具合に大幅に目減りしてしまいます。
輸出企業がドル売りの予約を入れると銀行はドルを借りて金利を支払います。そのドルを売って円にし、円での運用金利を受け取りますが、借りた金利と受け取る金利の差額が輸出企業の為替予約から差し引かれる仕組みなので、低金利では金利差によるディスカウントが大きくなるという不具合が生じます。
輸出企業が経営を安定させる為に円安の時に何年も先の予約を入れれば良いと思われるかもしれませんが、金利差が大きいと簡単ではありません。2年も先の予約を入れれば、120円が110円の受け取りになるようなことが起こります。日本だけがゼロに近い金利で張り付き、ユーロや米国といった主要通貨で金利上昇すると弊害も大きくなります。
景気のことを考えれば金利は低い方が良いでしょうが、世界的な流れの中で金利は変動し、上昇させる政策も有り得るのではないでしょうか。また、それだけ高い金利を受け入れるだけのファンダメンタルズに早くなって欲しいものです。
日経平均は11000円台ではこれまでのTOPIX主導の上昇からハイテク主導の日経平均優勢の上昇へピッチが上がる可能性が考えられます。急騰とそれに見合う将来の急落に一段と用心すべき場面に入ってきたと見ています。ボラタイルだからこそ収益機会が大きい場面としたいところです。
2003年9月17日(水)
利食い後の「買い直し」に注意。
日経平均は本日高く寄り付き過ぎ、高値水準を維持出来ずに引けました。デイトレが非常に多くなり、あまりの強気に同調していては上手く回転が効かないのも当然でしょう。大引けにかけて伸び悩んだのは利食いが増えたというよりデイトレ狙いの失敗玉の整理で甘くなったのではないでしょうか。大手銀行株にその動きが典型的に出たようです。
それでも、TOPIXに比べると日経平均はこのところ出遅れ感があります。ハイテク株の多いナスダック指数の堅調で日経平均がTOPIXに対する出遅れを取り戻すような動きがまだ続くと見ています。どちらにせよ、本日のようにボラタイルな展開が当分続くことは覚悟すべきでしょう。
こうした時に、利食った後に急騰した場面を見ると投資家心理は「利食い」でも「損をした」気分になりがちです。利益を得た話ばかりがマーケットに充満し、買わなければ損をするような気持ちに駆り立てられるものです。投資を成功させるには「勝ち逃げ」が原則ですが、分かっていても、なぜか高くなるほど黙って見て居れず買いに出てしまい、最終的には群集心理的に買って高値を付けてしまいます。
活況な場面で追随買いをした場合、思惑と違えばすぐにロスカットし長く持たないことが基本でしょう。利食い後に雰囲気で買い直してしまったような引かされ玉を持つと売りに転じるべき場面で行動できなくなります。ある程度、日経平均は(出遅れ銘柄もありますが)「根拠無き熱狂」の場面でもあり、素早い判断が求められる時期になったと見ています。
2003年9月16日(火)
業績より需給の銀行株。
先週の見通しでも述べましたが、日本株は長年続いた「持ち合い解消売り」という最大の呪縛から開放された可能性があります。最も銀行の所有額が多かったトヨタが本日も急騰したことはご存知の通りです。そうした銘柄が上昇するということは事業法人側からの持ち合い解消売りも峠を越した可能性が充分あり、銀行株の需給が改善した結果、急騰する寸前の状態だったのでしょう。
勿論、大手銀行は構造改革が遅れており、収益の割りに人件費の削減はほとんどありませんし、戦略的に魅力のある企業という訳でもありません。あるいは、東京都の外形課税の訴訟での和解が買いの根拠という報道がありましたが、外形標準課税は来年度から一般化される予定で、銀行にとって悪材料が恒常化することに変わりがありません。
結局、本日は債券と株式が急騰する矛盾するようなことが起きたのは決算対策がピークを過ぎたことが大きいのでしょう。日経平均は11000円台のボラタイルな景色が見られる可能性が一段と増したと考えられます。
余談ですが、阪神タイガースの優勝のニュースを見ると、一概に日本はどうかと論じても東京と大阪ではまるで違うことを実感します。東京で巨人が優勝しても多摩川や隅田川に飛び込む人はいないでしょう。道頓堀川に5000人以上も飛び込む人がいた事実は関東では理解できないことかもしれません。株式投資においても地域ごとにかなり異なった傾向がありそうです。もしかすると、関西圏の投資家の方が動く銘柄に対して「ノリ」が良いかもしれません。
2003年9月12日(金)
持ち合い解消売りの減少で堅調か。
日本の銀行は今まで何年もかけて持ち株を処分し、大手行だけで既に8兆円程度の持ち株を処分したのではないでしょうか。どの銘柄も万べん無く売っていたわけですが、みなさんはその中で大手銀行が最も金額的に多く所有していた銘柄は何かご存知でしょうか?
実は、銀行所有の第1位はトヨタで第2位はホンダです。2銘柄とも「国際優良株」のイメージで外国人の所有が多いと思われがちですが、株主構成においては意外と「ドメスティック」だったことは知られていないことでしょう。
銀行所有株ランキングにおいて、トヨタとホンダは3位以下を大きく引き離してダントツの1位と2位でしたので、銀行の売り圧力は相当のものがあったことでしょう。現時点でどの程度残されているか知る由もありませんが、本日、この2銘柄が急騰したことは画期的な出来事かも知れません。それも、ただ上昇したというのではなく、ホンダは7月の高値を抜き、トヨタは買い気配で直近の高値を更新し、窓埋めもせず上昇するという上げっぷりの良さです。
昨年末、長期投資の個人投資家は長年所有していた「タンス株」を仕方なく大量に処分しました。機関投資家の持ち合い株も長期保有という意味で「タンス株」と言えます。それを180度方針を変え、延々と売ってきたことが株式市場にたいへん大きな重圧となってきたことはご存知の通りです。もしかすると、この2銘柄の急騰はその需給の分水嶺を超えたことを示す象徴的な出来事だったかもしれません。
日経平均の構成銘柄では割高と思われる水準まで買われる銘柄がある一方で、銀行保有額の大きかったグループは指数に対して出遅れ感があります。これらのグループが支える形で日経平均は意外に堅調ではないかと見ています。
2003年9月11日(木)
テロの恐怖と別の要因も。
9月1日に起きた日経平均の急騰(326円高)と本日の急落(309円安)は同じことが逆に行われたような印象です。1日の債券市場の暴落が株式市場を急騰させましたが、本日は債券市場が急騰し逆の現象が起きています。月初に本日の急落の伏線が既に引かれていた訳で、テロの恐怖から下げた市場というのはきっかけに過ぎないのでしょう。
また、今週9日(火曜日)にも債券市場の急落と株式市場の急騰があり、株式市場の堅調さが債券の運用担当者を慌てさせ、株式買いのパニックになり、それが行き過ぎて再び債券に戻ったというようなドタバタした動きを見て取れます。
結局、市場参加者はファンダメンタルズから1.6%以上の金利は行き過ぎだと見ていると言えそうですが、かといって、どこが適正な金利水準か分からず当面落ち着かない投資態度を繰り返すでしょう。資本市場はどのマーケットが最も有利か絶えず捜し求めて資金が移動する場ですが、株式も債券も適正値を探しあぐねて右往左往しているようです。
本日の相場も今月1日の急騰と同様に他市場から受けるテクニカルな動きが変動を拡大した面があり、過剰に反応する必要は無いと見ています。また、裁定取引に資金が多く集まっており、上昇も下落も変動を大きくする装置として無視出来ない存在になってきました。
日経平均は火曜と水曜に付けた10950円で明確な過熱感が無かっただけに、高値になったと決め付けるには不充分な状況です。11000円を超えるかどうかで相場の景色が変わると考えますので、11000円台を付けるかどうかを予想するより、その過熱した状態を期待したいところです。売り圧力の大きい10800円〜11000円の価格帯で跳ね返されただけに体制建て直しに時間がかかるかもしれませんが。
2003年9月10日(水)
11000円超えは急騰?
昨年の空売り規制後、日経平均は上昇を続けていましたが、3月になって11000円を突破すると僅か5営業日で12000円まで駆け上がったことがありました。それが3月のメジャーSQとも重なり売り方は悲劇でしたが、その後、3日間で700円の急反落というボラタイルなドタバタ劇となりました。
今回はSQまで後1日ですから極端なことは無いとしても、11000円から急騰した過去のイメージは強いものがあります。実際、このゾーンは動きが早くなる実績があり、急騰するかもしれません。急騰だけでなく、急落にも要注意の価格帯が上に控えていることになります。
日経平均は年金主体のTOPIX買いが中心で上昇に派手さはないものの堅調と見ています。仮に、11000円を超えた場合は相場の景色が変わるかも知れず、ボラタイルな「11000円超え」が実現するかどうか注目すべきでしょう。
しかし、株価がいくら上昇しても日本が手放しで喜べる状況ではありません。株安場面では出来なかった構造改革が株高の間なら出来ることがたくさんあります。ITバブルの絶頂期にどうして金融機関が高値を売らなかったのか不思議ですが、株式市場が活況で高い時期なら体質改善が可能です。株高を正当化するだけのファンダメンタルズの改善を急ぐべきでしょう。
2003年9月9日(火)
相場に中途半端は無い?
現物株の売買に対して先物・オプションの売買の大きな違いのひとつはSQで必ず区切りがあるということです。それまで、強気や弱気、中立、やや強気など様々なポジションを取りながらSQではひとまず勝敗がつくところが先物・オプションの面白い部分でもあり非情な一面でもあります。
例えば、テロ事件のあった2年前のこの時期はそれまで下げ続けた相場がSQに向けて更に最安値に一段と売られましたし、今回は上げ続けた相場がSQに向けて一段高になっています。その意味で、大きなトレンドが生じた場合のSQの「勝敗」は徹底し、中途半端に終わらない場合が多くあります。今回も売り方の完敗に終わりそうな勢いです。
また、あまり公平と言えない空売り規制のお陰で運用スキームに先物・オプションを多用せざるを得ず、建て玉がSQ毎に増える傾向があります。これらの「装置」が現物市場に与える影響は益々大きくなっていると言えそうです。その割にはデリバティブの売買を行わない投資家は全く無関心で過ごしているケースも多く不思議です。
日経平均は裁定残が積み上がっていることが気になる水準ですが、SQに関してはスプレッド市場がマイナス30円からマイナス20円で成立するようになり、ロールが無難にこなせる状況です。裁定買い残が威力を発揮するのはまだ先のことになりそうです。リスク要因として下げ相場に転換した場合に思い出すべきでしょう。金利上昇が気になりながらもSQは比較的高い着地ではないでしょうか。
2003年9月8日(月)
やがてデフレから確実にインフレになる。
今はデフレが継続している状態ですが、「本格的に景気が回復する」か「財政破たんが近い状態になる」かの何れかの理由で長く続いたデフレもインフレになる時が(何時になるか予想はつきませんが)やってくることは確実でしょう。
その為に、政府が無理にインフレを作る必要は無く、景気が本格的に回復するのを待つか、毎年30兆円以上も国債を増発していけばいつかは貨幣価値が大きく落ち、インフレになることは明らかです。0.09%の国債に個人が行列を作ったことが懐かしい時代が必ず控えているに違いありません。
前向きの理由で金利が急騰するか財政問題でそうなるか分かりませんが、国債を超低金利で管理し続けることはやがて困難な時代が来るでしょう。そうなった時の話ですが、「相対的に」株式を買うことが有利になる筈です。但し、後者の理由によって金利高となった場合は信用リスクに過敏となり、収益力や財務基盤の弱い低位株は敬遠されそうです。
今後、日本経済がどのような姿でデフレを脱却するのか見極めるべき重要課題となるでしょう。中でも、株式をあまり持たず外債もほとんど投資しない信金のような小さな金融機関においては「インフレ警戒」が皆無のように見えます。彼らをいつまでも「国債管理政策」が守ってくれるのかどうか保証の限りではありません。株式の大量の持ち合い構造のリスクが大きかったように、債券偏重もまたリスクが大きいようです。
日経平均はSQに向けて買い方の「上げ賛成」の動きがある一方で、金利高を警戒する当局の神経質な債券管理姿勢が綱引き状態になっているようです。本日もまた為替市場に円売り介入を実施したように投機筋も政府の出方を見極めているようで積極的に参加し辛い状態があります。
ただ、米国株安を受けての翌営業日でありながら、日本を代表する企業であるソニーや松下電器産業が人気となり、上昇したことはブルーチップに対する需給の変化を感じさせます。日経平均がそれほど上昇しなくとも需給悪のピークを過ぎたトヨタや武田などの代表銘柄が人気となり指数を支えることになるでしょう。
2003年9月5日(金)
管理相場入り?
為替市場で8月中は全くドル買いの介入をしなかった財務省ですが、突然、覆面を外して115円突破を阻止するような行動に出ました。債券市場においても国債の買入消却を進めるなど管理政策を強めています。当然、株式市場も過度に上昇すると金利の急上昇につながりますので「管理下」に置かれていると想像すべきでしょう。公的年金買いで上昇する銘柄が金利の急上昇後は率先して下げていることは意味深です。
日本の場合、米国と異なり株高が経済に及ぼす好影響は小さなものです。むしろ、金融機関にとっては(資金ニーズを伴わない)債券安の方が問題でしょう。金融機関としては債券市場を当局がサポートしてくれるなら、もちろん、株高を望むに決まっています。厚かましいのですが、出来ることなら「秩序ある株高」という管理相場を作って欲しいところでしょう。
日経平均はメジャーSQに向けて高値で清算を目指す動きが強まる場面もあると見ています。値嵩の225採用銘柄の動きや入れ替え可能性のある銘柄の動きなど指数に関係した個別の動きに要注意でしょう。高値を試すとしても「過度の金利高にならないことが条件」であり、管理相場として難しいコントロールを要求されそうです。
2003年9月4日(木)
負け組が作った強気相場。
日本や米国だけでなくドイツなども新高値を付け世界的な株高となっていますが、ファンダメンタルズの改善という分かり易い材料以上に買われ始めた印象があります。その一因がこれまで勝ち組であった(金利低下のトレンドを信じて)債券を買い上がっていたファンドが「負け組」になり、運用不振から債券売り株式買いに転換したことが大きいと見ています。
債券投資はもともと運用金額が大きく、それを株式運用で補うことはたいへんな作業です。金額的に株式市場は債券市場に比べると遥かに小さな市場ですから、無理に株高で債券安を補完しようとすると株式が急騰することもあるでしょう。債券中心の運用をしていたところが今や負け組となり対立相手に加担して押し上げる全く逆の作用を及ぼしたようです。
その一方で、負け組の象徴でもある金融機関が債券の含み益を実現したい時期に、下げ始めた債券市場を見て益出しの売りを拡大し下げに拍車をかけた可能性があります。それが景気回復=金利高のムードを一段と高める結果になったのではないでしょうか。そうした機関投資家が否応無く高値を買い続けているようです。
とはいえ、金利も高くなり過ぎると、例えば生保の場合、株式運用を全くやらなくても新規契約に対して予定利率を充分カバーできることになりますので、行き過ぎた金利高は株式に魅力がなくなってしまいます。生保などはこれ以上金利が上がれば債券運用だけで確実に利益が出せますので株式運用の必要性を感じなくなるのではないでしょうか。
日経平均は金利上昇を警戒する金融当局の債券への介入姿勢を気にしながら過熱感を収めている場面ですが、債券市場がコントロールできるようなら再び買われる場面があるでしょう。日銀の国債管理政策が注目点となりそうです。国債市場が日銀の「管理下」に置かれた事は債券のパニック売りが防止されることを意味し、反対に、週初のような株式のパニック買いも起き難くなったと見ています。
2003年9月3日(水)
企業再生のあり方。
先週土曜日の日経新聞に日本電産の永守社長のインタビュー記事が掲載されていましたので、お読みになった方も多かったと思います。その中で企業再生について、永守氏は『破たん後に借金を棒引きしてもらって再生するのは誰にでもできる。最近の企業再生は弁護士や会計士が幅を利かせているが、本当に再生請負人といえるのか。破たん後に人を大部分入れ替えるより、生え抜きを活用した方が求心力が働き、長い目で見ても強い企業になる』と述べています。多くの経営者に聞かせてみたい核心を突いた発言です。
例えば、破たんした青木建設に対する高松建設による「支援」やレオパレスのダイア建設への出資、野村系企業のハウステンボス「支援」などは債権放棄後の再生であり、ハゲタカファンドの行動と基本的に同じで、報道で使われる言葉が間違っているようです。『借金棒引き後の再生は誰でも出来る』ことであり、「再生ビジネス」として別の見方をする必要があります。再生ビジネスの場合はどこかにツケを回しているだけになる可能性が充分あります。
企業再生は単なるリストラでなく、生え抜き社員を生かして売り上げを伸ばすような人材活性化策を手本にすべきでしょう。敢えて言うなら、公的資金で生き延びている銀行にゼロに近い金利で預けたり、再生できない経営者のいる会社に投資するより、永守氏に運用を任せたほうが余程良い結果になりそうです。彼自身の会社や日本電産の買収した企業に投資する方がはるかに魅力的です。
日経平均は高値圏での揉み合いとなり過熱感が収まれば上値を取る可能性もあると見ています。債券売りの株式買いの場合、資産の比率の差が大きく少しの移動でも株式市場には大きなインパクトがあります。債券市場が多少戻ったとしても極端な債券偏重が修正される動きが再発して株式を支えることになりそうです。
2003年9月2日(火)
「債券のパニック売り」と「株のパニック買い」
一般的にヘッジファンドが「債券売り・株買い」を実行して利益を得ていると思われているようですが、それで利益を得ているヘッジファンドよりも、むしろ、日本のデフレ傾向が続くとして債券買いを続け、大きな損失となったヘッジファンドの方が多いと見ています。彼らは一定の限度を越えて債券が値下がりした為に、ポジションのヘッジとして株式先物や株式を買わざるを得なくなったのではないでしょうか。
株式を買うといっても既に債券市場に資金を投入していますので、株式買いの資金として債券を大量に処分する必要があります。債券市場と株式市場は逆相関性が強いので損失を食い止める為に株式買いに走った結果、債券はパニック的な売りとなり、株式はパニック的に買われる一因となったようです。
政府は「経済情勢に見合った金利上昇は問題ない」とコメントしていますが、果たして、「経済情勢に見合った」金利上昇かどうかは意見が分かれるところです。実際、金融機関に借り手が殺到して手持ちの国債を売って貸し出しに応じたというような景気の良い話は聞えてきません。金融機関が国債を売ったとすれば、債券の含み益を実現して中間決算を良くしたいという思惑があってのことかもしれません。長期的に金利が底を打ち株式が買われるトレンドが発生しているとしても目先は過熱感があると考えるべきでしょう。
日経平均はこうしたパニック的な過熱感が出たところで小休止しながら、SQに向けて高値圏で推移することになるでしょう。政府が「金利上昇は実体経済を反映している」とする間は債券のパニック売りが何度か繰り返されそうで、株高優先の政策として評価されるでしょう。しかし、金利高を無視できる状態で無いことも確かで難しいコントロールが必要です。
余談ですが、かつて、「株安はオンライン投資家の売りが原因だ」と名指しして非難した政府はUFJやソフトバンクを集中買いをしたオンライン・トレーダーに対して過去の間違いを反省してもらいたいものです。彼らによって銀行株が中間決算前に上昇しているのですからお礼を言っても良さそうなものです。
2003年9月1日(月)
株式市場も異常気象並み?
8月の天気予報は週間予報で半数以上の日が間違いとなり、その意味でも「記録的」だったそうです。ただ、間違いの理由は合理的に説明できます。例年なら、太平洋高気圧が大きく張り出しているのが夏ですから、予報がそれ程間違うことはありません。
どうして予報官が半数以上も間違ったのかと言うと、例年に無くオホーツク高気圧が太平洋高気圧と対等に張り出し日本を覆っていた為に、2大高気圧に挟まれた前線が少しの力関係によってどちらでも簡単に振れてしまう状況が続いたからです。これが異常気象となり予報の精度が極端に落ちることになりました。
そして、これは最近の株式市場にも当てはまることでしょう。9月中間期ということもあり、金融機関などの大きい売り手があるものの、ヘッジファンドや公的年金、海外年金といったビッグ・プレーヤーが睨み合った状況があり、そのせめぎ合いの中で振れ易い状態が出来ています。そして、ある程度の水準訂正を行うと再び大きな勢力の間で睨み合いになると考えられます。気象とマーケットは物理学的に同じような系にあり、「気圧配置」が同じ様になれば「異常気象」も当然似てくるということでしょう。
こうした中での戦略は、予測してポジションを取るより、銘柄間のローテーションの差を利用したロング・ショート戦略や相場の過熱場面を待っての逆張りの戦略が良いでしょう。オルタナティブの戦略ではロング・ショートになりますが、アウトライトには、小康状態では仕掛けず、振れた方向に対して最初は順張り、過熱感を見て逆張りということになるでしょう。
日経平均は米国が休みであることから、かえって投機筋も気にせず買い進めた感があります。明日はNYを気にする必要がありますので、一方通行というわけにもいかないでしょう。また、債券入札で債券市場の流れが変わるかどうかも注目です。引け後に135円台に突入した債券先物が明日も撹乱要因になりそうです。ただ、ファンダメンタルズでは、これ以上の金利上昇は現実的でないというところまで来つつあると見ています。
2003年8月29日(金)
米国連動の写真相場。
最近の日経平均は見事なまでNYダウの写真相場を演じています。円高や総裁選など大きな材料もあるのですがほとんど相場に影響を与えず、ひたすら米国市場のコピーとなっているように見えます。
そもそも、日銀のドル買い介入が米国に流動性を供給し、その資金が回りまわって日本株を買うという「日米合作のバブル創造相場」が背景にあると考えれば写真相場になるのが当然と言えます。もちろん、株高の基本はファンダメンタルズの改善であることは言うまでもありませんが、ほぼ織り込まれた可能性があります。
写真相場の相手の米国が3連休とあっては週明けの東証の売買金額は急減し、方向性が出ることは期待できないでしょう。一方、相場に影響が大きい数少ない国内要因としては、来週2日の10年国債の入札が気になります。最近の債券相場の乱高下で入札がどのような結果になるか株式の関係者にも注目されそうです。
それにしても、1億株を超える大商いでりそなHDが100円大台を回復したり、山水電気が連日大商いになるような「モラル・ハザード」相場はあまり強気になるべき相場とは言えません。物色人気の質の悪さが気になるところで、アウトライトのポジションは多く持たないほうが良さそうです。日経平均はレンジを大きく変えるにはどちらにも力不足で連休後の米国が大きく動かない限り、今週と似た展開でしょう。
2003年8月28日(木)
ダイア建設とセザールの差は何処に?
同じマンション分譲会社でもセザールは倒産し、ダイア建設は国が救済する形になりました。他にも老舗どうしの例では、福助は産業再生機構の手が及ばず倒産し、三井鉱山は救済されることの差も明確ではありません。特に、同じマンション業者として(決算報告上)債務超過でなかったセザールは倒産し、債務超過のダイア建設は公的援助が受けられるとあっては実に不可解というものです。その区別を合理的に説明してくれる報道はどこからもありません。
再生機構が援助をする限りは公的な意義が大きい方を優先すると思われがちですが、そうでも無いようです。再生機構は福島の小さな百貨店を救済したり熊本のバス会社も救済しますから、社会的に影響が大きい企業を優先するわけでもありません。(もし、その意図があるなら大手流通企業や大手銀行を国営化したほうが早道でしょう。)
結局、同じマンション業者であるセザールとダイア建設の差は「取引銀行の差」ぐらいしか思い当たりません。三井住友銀行主力のセザールとあさひ銀行(りそなHD)主力のダイア建設という差です。再生機構は公的な立場ですが、企業選別の具体的な判断基準は示されません。やはり、構造改革や経済政策というより銀行救済色の強い「特殊法人」がスタートしたのでしょうか。マーケットはかなり再生機構に期待しているようですから、裏切らないようにして欲しいものです。
日経平均はヒストリカル・ボラティリティの低下が示す通り、これまでのボラタイルな動きから比較的狭いレンジ相場へ移行しつつあるようです。本日は海外の投機筋も3連休前でポジションの縮小に動いたことでしょう。背景に金利上昇を抑えようとする当局の強い介入姿勢があったことは言うまでもありません。
指数を引っ張ってきた半導体関連銘柄や大手銀行株に過熱感が見られることも上値を重くしそうです。また、週末の経済指標を見ようとする投資家も多いでしょう。短期売買が多いだけに週末は手控えムードが強くなりそうです。
2003年8月27日(水)
東証1部への大型上場毎に年金が損をする。
エプソンに続いて東証1部へ直接大型上場したのがNECエレクトロニクスです。これをTOPIXの指数に算入すると決めらていた25日は指数とのトラッキング・エラーを避けるために大量のアジャスト買いが入り、NECエレはストップ高となりました。
しかし、TOPIX指数に単純に連動させるだけの運用は特定の日に本来の企業価値と無関係に当該銘柄を高く買う一方で、買い付けのための資金を売る必要の無い日に単純に売ることになります。NECエレや同日にTOPIXに新規採用されたニッセンもその後は「何も無かった」ように静かに値を消していますので、如何に無理をして集中的に買ったか歴然としています。
指数連動型の運用(パッシブ運用)は銘柄入れ替え毎にこのような乱暴な作業を繰り返しますので、実際は長期運用に適していない可能性があります。最も象徴的な例は日経平均の30銘柄入れ替えのケースで、2000年4月17日以降とそれ以前の指数では3千数百円の違いが生じたと言われています。また、当時の指数連動型の投信の保有者や機関投資家の合計で1000億円を超える被害があったとも言われています。
今後も東証に大型上場がある毎に指数連動の為の運用が過剰な売買を行い、自ら指数を歪めて執行損を繰り返すことになるでしょう。「代行返上」とは企業を選別するアクティブ運用を止めて指数連動型の無味乾燥な運用をすることを意味します。これは企業が選別・淘汰される場としてのマーケットの優れた機能と正反対の機能を拡大しますので年金運用が大きくなればなるほどマーケットを歪める事が問題になりそうです。
さて、日経平均は戻り高値更新となりましたが、すぐさま売られ、予想した通りのボラタイルな展開となりました。勢いのある相場ならこのような反落は見られませんので、レンジ相場を形成する兆しと見ることも出来そうです。オプションのインプライド・ボラティリティが指数の高値更新の場面でもあまり上昇しなかったことにもその兆候が見られます。とは言え、債券先物に振り回される動きが完全に収まったとは考え難く、まだ、「余震」に揺さ振られることがあるでしょう。
2003年8月26日(火)
債務超過会社の株が上がる不思議。
産業再生機構は三井鉱山とダイヤ建設を支援する方向と報道されました。どちらも大幅な債務超過企業と監査報告されているにもかかわらず株価は急騰しています。連結で三井鉱山が353億円の債務超過、ダイア建設が753億円の債務超過です。解散価値がゼロ以下の会社の株式が100円以上であったことがそもそも不合理ですが、再生機構は経済的な混乱を避ける為に税金で援助するシステムであって、既存株主を救済することが目的ではない筈です。
仮に、株主の権利をそのまま認めるならりそなHDへの税金投入で株主責任を問わなかった「竹中=木村路線」の延長として定着しかねません。りそなHDの株主責任が問われなかった結果、大株主の野村HDは税金でりそなHD株を高値で売ることが出来ますので大助かりです。日本の納税者はかなり心が広いようです。
「政府が関与すれば株主責任を問わない」という方針はりそな問題が発端ですが、りそなHDが株主責任を問う形で完全国有化した場合、果たして、その後の株高は変わったでしょうか。
株式市場の持つ優れた機能は選別機能であり、敗者救済は護送船団方式の延長で、新しい企業を育てる活力を削ぐ結果になります。本日は優良企業が売られる場面でも債務超過企業が買われました。「負け組」企業に資金が集まる市場は合理的な資本市場とは言え無いでしょう。
日経平均は再度、債券先物の仕掛けを伴って上値を試されそうですが、ボリュームが伴わない上昇に対しては判断が分かれるでしょう。裁定買いで上げる相場は逆も大きくなりがちでボラタイルな展開になりそうです。
2003年8月25日(月)
物色人気の質の悪化は天井圏の証。
最近、中心となっている参加者はディーラーやオンライン・トレーダーといった短期売買を主体とする層ですが、常に売買対象となる大手銀行やソフトバンクを除くと大商い銘柄の質の悪化が目立ちます。債務超過ではないかと思われるような企業が真面目に(?)売買対象となっている光景は異常なものがあります。
株を買うことのオーソドックスなスタンスはその会社の株主となって成長を楽しむことだと思いますが、ここへきての物色傾向は益々そのことと対極のマネーゲームへ傾斜してきたようです。昨年末ならいつ倒産してもおかしくないと思われていたような銘柄が結構な株価まで上げています。中には実際に業績が回復しているものもあり、玉石混交ですが、どうみても全くのマネーゲームに過ぎないと思われる「人気銘柄」も多くあります。投機は当然認められるべきことですが、この傾向が強いほど天井圏特有の状態と考えられ、下落リスクはその分高くなります。
長期投資の個人投資家の多くが昨年去っていっただけに、今年は「株式投機元年」とでも言うべき年です。そうしたスペキュレーターにとって信用リスクに無警戒になり過ぎるとその先に落とし穴が待っているかもしれません。
日経平均はどの程度になるか予測は難しいものの、おそらく、米国の調整局面入りを受ける形で日本株も調整するでしょう。このところの上昇局面でファンダメンタルズや個別の業績面で良い材料を大半消化したと見られ、新規の好材料に反応が鈍く、良くて時間的な調整があるといったところでしょう。
2003年8月22日(金)
流石に上値が重くなる水準。
どんなに体力がある人でも全力疾走すれば息切れして当然です。日経平均はほとんど休みらしい休みも無く上昇してきただけに、そろそろ休憩が欲しいところでしょう。数日前に既に調整すべきところでしたが、無理矢理上値を買い続けたような相場になりました。先週の予想通り、休み明けの国内参加者がやや焦り気味に上値を積極的に買い進んだ週となりました。
その結果、買い疲れ感はあちらこちらに見られますが、松下電器産業、阪和興業、楽天など個別に好材料が出た銘柄のほとんどが「織り込み済み」の反応を示したことが強気相場の限界を示したと言えそうです。全力疾走の後だけに、上昇を続ける為にも呼吸を整える時間が必要でしょう。
一方で、悪材料にどのような反応を示すかが注目されますが、日経平均採用のイトーヨーカ堂が大引け後に下方修正を発表したことが週初どの程度影響するかも注目したいところです。
また、世界的な投機資金が日本株を買い、JGBを動かしましたが、「予定通り」為替を円高方向で仕掛けているようです。この仕掛けが介入姿勢の強い政府・日銀にどの程度通用するかも注目点でしょう。最近、ヘッジファンドに資金が集まり過ぎた結果、彼らもまた資金が多過ぎて「運用難」になりがちという話もあります。株・債券・為替それぞれの市場に行き過ぎが当たり前のようになってきたことに慣れる必要がありそうです。
2003年8月21日(木)
株高で大手銀行は幸せ?
市場では株高で大手銀行の株式含み益が増大するから銀行株が買われていると解釈していますが、銀行株の上昇はファンダメンタルズが改善すれば不良債権が減ることへの期待と売られ過ぎの反動が主なものでしょう。
銀行は今年の1〜3月に大量に持ち株を処分しており、現金を国債に変えた結果、株高を率直に喜べなくなったのではないでしょうか。例えば、複数の大手銀行が持ち株を大量に日銀に売却したテルモ(4543)は日銀が筆頭株主(実際は信託銀行名義で表面に出ません)になっていますが、この銘柄の売却価格は推定で1800円程度です。それが、本日の引け値は2345円です。業績の悪い企業ならともかく、テルモは今期最高益の予想でしたからファンダメンタルズから考えて売る必要はありませんでした。
銀行は「リスク資産の圧縮」や「自己資本の充実」、「金融危機回避」といった掛け声で日銀に最も安い時期に大量に売ってしまい、テルモのように売却後に3割近くも値上がりされ、代わりに買った「リスクの小さい」国債が値下がりしたのでは大手銀行は決して嬉しいはずが無いでしょう。
このように考えると、銀行株を株高で買うのは本筋でなく、ファンダメンタルズの好転で実際に不良債権が減少することに根拠を求めるべきです。実際に不良債権が減らなければ銀行株高は砂上の楼閣になるしかありません。
さて、日経平均は「債券売り・株式買い」が一服したものの、公的年金らしき買いでTOPIXが買われ、引っ張られる形で上昇しています。先月の22日から28日にかけての動きと同様ではないでしょうか。
2003年8月20日(水)
税制変更で不動産の流通が拡大。
予想されていたことですが、不動産の流通が急拡大していることが報道されました。住宅や土地に値頃感が出てきたことと、供給側の都合が一致してきたことが主因ですが、4月からの不動産流通課税の大幅減税が効果を発揮していることも間違いないことでしょう。
不良債権処理促進の為に税収の比率が小さい割りに効果が大きいとされていた不動産取得税や登録免許税(登記の際の印紙代)の引き下げが今年からようやく実施されました。その結果、買い手の負担が大幅に減少し、実質的な不動産の値下げにつながった効果は大きなものがあります。
デフレの場合、不動産は買うより借りた方がコストは安くなりますが、流動性が上がったことで今後も値下がりしたとしても、その速度はかなり緩和されると考えられます。不動産が値下がりしなければ借りるより買った方が良いと考える傾向が強まることは間違いありません。
また、不動産市場の拡大はオンライン取引で対面の比率が落ちた生損保や証券界の人材の受け皿となっています。大手の仲介業者は軒並み人員を増やしていることは証券界にも朗報かもしれません。不動産取引は手間がかかるのでオンライン取引というわけにはいきませんし、仲介手数料も3%プラス6万円という高率がバブル崩壊後もデフレの影響を全く受けずに維持されている特異な業界です。
また、法人の資産とし空いていた事務用の不動産がコンバージョン(用途変更)のスキームを使ってマンションなどに生まれ変わり、安く売り出されるというマーケットも生じています。税制変更や制度変更を少し加えただけで、不良債権処理や資産処分が進み、新たな「再生マーケット」が生まれ雇用が増えるという好循環があります。日本再生のヒントとして、高速道路をどんどん作らなくてもアイデア次第で経済は活性化できるということの一例です。
日経平均は一方的な上昇に対する調整場面が近いか、大きな調整がなくても高値で揉み合う水準でしょう。株式市場の一方的な上昇と債券市場の急落が続いた資本市場ですが、次は、決まったように為替市場が動かされます。
ドル・プットのプレミアムがたいへん安い状況ですから国際的な投機資金にとって魅力的なターゲットでしょう。ドル=円の相場次第では再度の流動性供給が始まる可能性があり、日銀の行動に注目すべきでしょう。
2003年8月19日(火)
オンライン証券の「大商いリスク」
かつて、取引所が場立ちによる取引だった頃、大商いになると「笛吹き」が行われ、商いを一時中断させる為に「板寄せ」となることが良くありました。板寄になるとしばらく取引が出来ず、我慢するしかありませんでした。「執行リスク」は商いが少ない為に価格形成がスムーズに出来ないことが大半ですが、自動化された現在にあっても大商いで執行リスクが頻発するようです。
特に、オンライン証券での取引は旧時代の「場立ちを介しての取引」と同様のリスクを考慮しておく必要があるようです。大商いの本日、案の定、オンライン証券大手各社はほとんど例外なく何らかのトラブルを発生させたようです。
「つながらない」だけのトラブルなら複数口座があれば他社で取引可能ですが、厄介だったのは、注文を出したのに約定確認が取れなかったトラブルです。確認できない状態ではロスカットも利食いもできません。資金が人質に取られたような恰好です。また、発注したものの執行時間が遅れすぎて成り行きの場合の出来値がずれた例も多かったようです。
オンライン各社は約定連絡が大幅に遅れるような事態なら中途半端に注文を受けないようにすべきでしょう。現状では手数料が安いことを理由にかなり無責任な対応を取っていると言わざるを得ません。また、証券会社だけでなく、東証においてもシステムダウンの可能性があり、再び「物理的限界」を試されている状況です。
債券は20年物の入札が決して悪い結果でなかったように、実需面で金利高を肯定できる材料は不足気味でした。ところが、昨日同様、債券先物の引け前10分程度で大幅に売り込まれ、前回安値に近い水準で取引を終了しました。これは仕手筋が良くやる「引け値関与」の手口であり、債券相場の下落を意図的に演出するものでしょう。
日経平均先物も債券先物の急落を受けて、引け後に高値まで買い戻される結果になりました。投機筋において、景気が実際に良くなるかどうかは関心事では無いでしょう。債券参加者にファンダメンタルズの改善を扇動し利益を得ることが目的の筈です。個人投資家としては相場の撹乱者を上手く利用できるように立ち回るしかありません。債券先物の138円割れから日経平均の高値波乱を注意すべきでしょう。
2003年8月18日(月)
狙われた債券市場。
日本の金融機関はリスク資産圧縮の一環で株式を放出する一方、換金しても借り手の無い資金を国債の購入に回しています。その為に金利は「超低位安定」でしたが、債券は理論的に高値に限界があり、その点、株式と決定的に異なります。債券は(誰しも気が付いていますが)売り崩されると含み損が出るしかないという「欠陥」がありました。
大手銀行にとって使う先の無い資金は国債を買うしか方法が無いものの、それはいつ売り崩されるか分からない消去法的な運用手段です。ある意味で、どこかで含み損が出ることが分かっていてもそうするしかない自虐的な方法と言えます。銀行は安値で株式を「兆円」単位で売り払い、株高の恩恵は日銀が享受してしまう有様です。
公的資金は株式を買い支えた結果、意図せず債券の下落を招いてしまい、金融の安定を図ったつもりが銀行をいじめたようにも見えます。ヘッジファンドにとって、そのような政策の矛盾が絶好のターゲットになったのではないでしょうか。代行返上売りという政策の欠陥から生じた相場の歪みと合わせて、「債券売り・株買い」は彼らにとってたいへん魅力的なポジションに思われることでしょう。
140円割れの債券先物を売っても「空売り禁止ルール」がありませんので、買えるだけ買った金融機関に対して売り浴びせ、ヘッジ売りを引き出し、更に、株先を買うことで債券先物を売らせるという戦略が可能です。これは修正不能の金融政策の矛盾点を上手く突く合理的な仕掛けです。「修正不能」と言うのは当局は建て前上、株高を望んでいるという意味もあります。
日経平均先物はそうしたマニピュレーションで新値更新する可能性が充分あります。状況としてはヘッジファンドのやりたい放題という感じです。機関投資家も買わざるリスクから高値買いに追随するところも出るでしょう。しかし、それはヘッジファンドのような短期資金のなせる業であり、強気筋も弱気筋も今週は大いにチャンスありと見ています。
2003年8月15日(金)
高値波乱か。
本日の相場は来週の展開を予告しているようなところがあります。寄り付きから買い気が支配的で、6日連騰かと思わせましたが流石に強気に傾き過ぎた為に後が続きませんでした。来週も急騰すればその反動も起こるといった相場になりそうです。参加者の腕の見せ所でしょう。
相場においては、良く強気か弱気かという踏み絵のような議論になりがちですが、ファンダメンタルズに対して現状が過小評価か過大評価かの議論はなかなか結論の出ないことで不毛の議論です。
急騰した相場に対して更に強気を唱えることが「強気」を意味すると理解されがちですが、それは本当の強気ではありません。位置のリスクが大きくなってから強気を言うことはそれが当たっていても大きな価値はありません。強気なのか無謀なのか紙一重の差と言えます。本当の強気とは下げている時に買いを判断できるかどうかでしょう。
例えば、最近の機関投資家の「タンス株処分」の例で言えば、トヨタが3000円を割れていた時にどれだけ買えたかということになります。皆が見向きもしない時に断固買える投資家こそ強気の投資家と言えるでしょう。
ちなみに、今年、最も強気だった時はイラク問題の時で、『霧が深い時ほど買い場』だと述べました。しかし、そのような相場低迷期に限って、強気を言うと「無謀だ」と非難されるものです。その頃、弱気だった投資家が今、最も強気なのかもしれません。
2003年8月14日(木)
日本電産と富士通の差。
1949年にカメラ用シャッター会社として設立されたコパル光機製作所は1961年に東証2部に上場するまでに成長し、社名をコパルと変えました。しかし、上場後は多角化が上手くいかず84年に富士通系の企業として資本参加を受け入れ再生を計ります。
その後、富士通はコパルを14年間もバックアップしながら経営を軌道に乗せることが出来ず、第三者から見れば投げ出したような形で98年に日本電産に経営を譲りました。富士通の社員数は3万4千人余、日本電産は僅かに1099人です。これは関係あるかどうか分かりませんが、平均年収は富士通が751万円、日本電産が482万円とこれも大差があります。
日本電産は巨大企業富士通と比べると弱小勢力に過ぎません。人の数で31倍の差があり、富士通の人たちの年収は日本電産の5割以上も高く、年収に見合って「優秀」な筈です。しかし、コパルの経営に関しては電産コパルとなってから株価は富士通の傘下企業時代の5倍以上に大差をつけられています。これは一体何を示しているのでしょうか。なぜ、巨大企業はコパルを再生できなかったのでしょうか。
この分析が日本再生の鍵になりそうです。そしてまた、日本電産は他の大手企業を尻目に三協精機の再生でお手本を見せようとしています。永守流の合理性は、「報酬を受け取らず株券で受け取る」彼のやり方からも分かるように株主本位の経営の手本と言えそうです。
日経平均は再びボラタイルな動きになってきました。株価指数のみならず債券先物や為替の変動まで巻き込みそうな勢いがあり、投機的な売買で乱高下しそうな気配です。今回の上昇は国内勢の参加が少ないところで行われた為に、週明けに買わざるリスクを感じて高値を国内勢が買う可能性があり、海外勢に比べ仕掛け遅れた感があります。週明けの国内勢の買いが高値を付けるまで収まらないのではないでしょうか。
2003年8月13日(水)
チャート分析の限界。
昨日に続き、検証の為の「良い素材」として三協精機を取り上げたいと思います。三協精機が日本電産グループ入りするという発表で連続ストップ高した翌日、普通に売買されるようになった460円どころでもまだ買い余地があると判断し強気でしたが、多くの方からこのような高値では買えないと指摘されました。
買わなかった方々に共通した点は、いつも買う前にチャートを充分に検証する堅実な方々だったということです。しかし、三協精機のように会社の経営が不連続に変わるような場合や資本金がいきなり2倍になるような変化が起きた場合、過去の株価を基準にする事にどれだけの合理性があるのか疑問です。
つまり、資本も経営陣も全く別の会社になってしまったのですから、この場合、「別の銘柄」として考えることも出来そうです。チャートは過去の記録であり、三協精機の軌跡は「駄目会社」の時のものであって、冴えない過去の記録を参考にしても仕方が無いのではないでしょうか。むしろ、過去が邪魔で買えなかったと言うべきで、そのあたりがチャート分析の限界かもしれません。
また、以前に、持ち合い解消売りで、例えば、みずほFGの浮動株が時間を経る毎に異なっているので、気が付けば「違う銘柄」になっている可能性があると書いたことがあります。株主構成など主要な事柄で大きく変質したケースが構造変化で多々あり、過去の記録が分析に邪魔になることさえあり得ます。何年か経つと違う銘柄に「変質」してしまうような場合はチャート重視派の方にとってバイアスが必要でしょう。
日経平均は売りも買いも投機的な短期資金が多く入り込む状況にあり、再び高値波乱の時が近付いているようです。売り買いとも時間枠を狭く設定する必要がありそうです。日本よりも米国に特徴的に現れるような気がしますので、やはり、海外の状況が決め手になるでしょう。
2003年8月12日(火)
会社は従業員の「福利厚生施設」ではなく株主のもの。
三協精機が日本電産の傘下に入ることが発表されてから三協精機の株価は上昇を続けています。両社の事業内容は良く似ていますが資本提携前の株価は約20倍の差がありました。同じ様な業務内容で株価が20倍というのは根本的な差があったからということになります。
違いは端的に、「株主を大事にする経営をしているかどうか」でしょう。日本電産の社員は猛烈に働くことで有名で、社員にとって楽な会社ではありません。しかし、赤字で会社が潰れるまでのんびり働かれては株主だけでなく社員も堪りません。会社が潰れては元も子もありません。ちなみに、単体での比較で1人あたりの売り上げは日本電産の社員が三協精機の社員の約2倍の売り上げになっています。
どこかの国の官僚が「納税者の為にならない特殊法人」を増殖させるごとく、株主を軽視して会社を従業員と役員の「福利厚生施設」として利用しているような会社がたくさんあります。オーナーでも無いのに社長を「世襲」した公共企業すらあります。会社を役員や従業員のものから株主のものに取り返す経営が日本電産の永守氏の役割であり、株価に期待感が反映されていると見れます。
永守氏は買収先の社員に必ずアンケートを実施し、その中で「自分の会社が倒産すると思ったかどうか」を聞くそうですが、99%以上の社員が倒産すると思ったことがないと答えたそうです。危機感のない会社は「従業員の為の福利厚生施設」となり、株主は駄目になるのを待つばかりで報われません。もちろん、個人投資家は株主重視の会社の応援をすべきでしょう。
日経平均は先物主導で3日続伸しましたが、先週までは先物主導で下げていたので反動高と見ることも出来ます。出来高が少ないと再び先物主導で下げることもあり得ますので上値を追える状況ではないでしょう。
2003年8月11日(月)
信用期日廃止の松井証券「新制度」
個別銘柄は高値や安値の大商い後の6ヶ月期日に再び大商いの急落や急騰劇が繰り返されてきたので、松井証券が率先して期日を廃止する新制度を作ったことは評価できます。しかし、信用買いだけで、売りは出来ないことや既存の制度より金利が高い点など投資家に有利かと言うとそうでもありません。
米国では売りも買いももともと期限が無く、日本は信用制度の改善が遅れていました。反対に、信用制度の空売り規制など都合の良いところだけ「世界標準」を取り入れる規制強化があります。
ところで、信用取引で何十年と続いている「投資家への不合理」が存在しますが、誰も不思議に思わないことがあります。それは、信用買いの際に30%の現金証拠金を入れているのに、買い代金の100%分に対して金利を取られる点です。証券会社はどの会社でも「顧客第一」を掲げていますが、「金利は70%分にします」という顧客サービスは聞いたことがありません。
また、信用売りは買い方への融資になりますから金利は受け取れますが、これも懲罰的に金利を取っています。信用売りは急落時の買い支えになる保険の役割がありますので、何ら懲罰的な金利を取る必要はありません。行政に偏見があるからでしょう。投資家は証券界の「常識」を少し疑ってかかる必要がありそうです。
日経平均は先週の予想通りにリバウンドしていますが、売買高は少なく、指数の信頼性は乏しい状態です。積極的に参加するプレーヤーが限定される時期だけに先物の大玉で方向が決まる地合いで、一部の短期売買資金によるマニピュレーションで動かされることになりそうです。
2003年8月8日(金)
「良い金利高」と「悪い金利高」
デフレ経済が終われば避けて通れないのが金利高ですから、株式市場にとって金利高は実は歓迎すべきことと言えます。金利が高くなることは企業に設備投資意欲が出て資金ニーズが生じた結果であり、金利高でも株式市場は強い動きになるはずです。
しかし、この金利高にも「良い金利高」もあれば「悪い金利高」があります。「悪い金利高」とは資金需要の盛り上がりでなく財政悪化・国債増発によってもたらされる金利高でしょう。米国の大型減税が設備投資に大きな影響を及ぼさず財政悪化につながると悪い金利高になり、株価も流動性相場が否定され、業績相場に向かうほど強くなれずに低迷することになります。
米国にその傾向が出ているのが今の状況でしょう。設備投資が景気対策で期待したほどに盛り上がらず、いわゆるジョブレス・リカバリーと言われるリストラ回復の延長線上には上昇トレンドが描けません。
日本の場合も、毎年大量に国債の発行が増えていることがあり、何ヵ月後、あるいは何年後か分かりませんが、いずれ「悪い金利高」が起きることは避けて通れないことです。悪いデフレの後に悪いインフレにならないように舵取りをしてもらいたいものです。
さて、来週の日経平均は指数の閾値でもある9200円前後を意識する展開で、ある程度下げた後だけに戻りを試す場面もありそうです。戻りが鈍いと再び売られる可能性が大きいと見ていますが、抵抗ラインがあるだけに大きく売り込めずに揉み合うかもしれません。
2003年8月7日(木)
株価だけで信用判断する年金。
4月末に大手銀行のみずほが5万円台、UFJが8万円台の安値を付けた時に実態を反映していないと金融担当大臣が説明したことがあります。では、同じ「官」である公的年金が「実態」を個別に判断して運用を決めたかといえばそれもありません。
公的資金の運用では株価が100円を割れると自動的に運用から外すという決まりがあると言われています。また、3月に買いを集中させた反動で4月は買わない時期でもあります。実際、4月に10万円以下で大手銀行株を売った最大手は公的資金ではなかったのかとさえ言われています。みずほFGやUFJが10万円割れとなった途端に加速して売ったのは「身内の反乱」だった可能性があります。
本日も「株価100円」の思惑でみずほFGが10万円割れした瞬間に下げが加速していました。ファンダメンタルズと無関係な基準で株価が歪めらるのは当事者にとって迷惑なことでしょう。株価が100円以下であった企業で何社かが復配を検討していることを考えると「株価=信用」ではなく、運用担当者は個別に中身をもっと吟味して欲しいものです。
日経平均はファーアウトのオプション建て玉が両サイドで大商いになり、8月物に比較して残高が急増していることを考えると、かなり強弱感が対立しているようです。水準的に目先リバウンド局面と見ていますが、下げ過程で悲観人気が盛り上がらないことを考えると戻っても迫力の無い戻りになりそうです。
2003年8月6日(水)
世界で最も動かない通貨「円」
為替市場ではこの数ヶ月だけでも「円」を除いた通貨はユーロを始めとして実に大きく変動しています。円だけが世界で何が起ころうと地味な変動しか起こさない特殊な値動きとなっています。ユーロや、ポンド、カナダドルなど円に比べて変動率がずっと大きいのですが、通貨が変動したからといってその国の経済が致命的な大問題が生じたという話は聞きません。
通貨のボラティリティを小さくしているのは勿論執拗な介入を続ける当局の関与が大きい為でしょうが、他の通貨の普通の変動に比較すればやり過ぎでしょう。かつて、現りそなの大和銀行NYのトレーダーが外債市場で大損害を出したことがありますが、過保護の市場で戦っていたトレーダーが「世界標準」で戦った場合どうなるのかの見本のような気がします。結局、過保護な市場で育ったトレーダーの損失まで税金で面倒を見る結果になったのはご存知の通りです。
変動を抑えることが果たして本当に必要な政策かどうか良く考えてもらいたいものです。株式市場でも公的資金が大きな影響力を持っていますが、そのような制度を持つ国は先進国では例がありません。世界に個人マネーが出ていく時代にもっと市場で鍛えられても構わないのではないでしょうか。
日経平均は米国株安の影響以上に売られていたこともあり、戻りを試す場面があると見ています。ただ、アノマリーな売りが出やすい時期で、戻りに対して疑心暗鬼となり追随する向きは少ないと思われます。
2003年8月5日(火)
同じ意見多い時は危険なサイン。
日曜日のTV番組で強気と弱気を代表するストラテジストが対決したそうです。7月までの上昇で最も美味しい場面は既に終わっているような時に再び8000円台に戻るか11000円に上昇するかの議論はあまり意味がないことです。景気判断は世界的に循環サイクルが読み辛い経済システムになり、専門家でも予測は困難でしょう。そのような中途半端な水準で高いか安いかの予断を持って相場に臨む必要性がありません。
その議論で弱気派が四面楚歌だったそうですから、そのこと自体は調整が長引く可能性を示唆しているかもしれず、興味深いことです。どの投資家も自分のポジションに絶対的な自信を持っていませんので、ネットや雑誌などで自分と同じ意見を目にすると安心します。時には、わざわざ同意見を求めて閲覧する場合すらあります。
しかし、自分の考えと同じ意見が多いなら、多いほどリスクと考えるべきで、安心するという行動は理屈に合いません。TV討論で強気派が圧倒的に支持され、出席者が得意気であったなら、すでにその段階で支持の多かったほうの意見が間違っている可能性があり、慢心すべきで無いでしょう。投資家は評論家などが自分と同じ意見であればあるほど用心深くても良いぐらいです。
そもそも、真の強気とはリスクが小さいと判断できる時に敢然と買えることです。ここでは、イラク問題で見通しが立たない時期に既に「霧が深い時程買うべきだ」としました。水準が相当上げてきたところで強気か弱気かの踏み絵を試すような議論は参加するに値しないものです。
ところで、目先の日経平均はある程度の安値を見たことで多少戻れる状態にあると見ていますが、外国人投資家の強気姿勢に変化があり、大きく戻す力は無さそうです。外国人投資家にとって、為替が円安気味の時は、価格リスクと為替リスクの両面で買いを入れ難く、力強さに欠ける展開は仕方のないところです。下げれば買う公的年金が出るなら短期売買が追随する決まったパターンが見られるでしょう。
2003年8月4日(月)
真の「投資家」は株価が下がって喜ぶ。
個人の株式税制の変更で個人「投資家」が減り、「投機家」の比率が圧倒的に高くなりました。少ないながら個人「投資家」は、普通、買った株が値下がりするとがっかりすることが大半ですが、大きな利益を株式で得ている投資家の中には株式が値下がりすると意に介さないばかりか喜ぶ人がいます。
つまり、最初から狙った銘柄を一度に買い切らず分散して買うものだと決めていますので、値下がりして多く買えることを喜びます。普通はナンピンで損が大きくなるといって嫌われる方法ですが、結局、株式で大きな資産を作ってきたタイプはこのようなじっくり型であったと思います。
ナンピン損を大きくしない為に銘柄選定が決め手です。ふだん、非常に苦労する筈の銘柄選定ですが、銀行や企業年金がブルーチップをどんどん売ってくれるお陰で倒産リスクのほとんどない銘柄がバーゲンになっていると言えそうです。投資家の状況判断も大切ですが、資産配分というリスク管理が成功の秘訣でしょう。「株価が下がって喜べる投資家」は強いということです。
日経平均は超目先では買い場と言える段階ですが、もう少し長めのスパンでは弱気継続と見ています。この辺りは参加者の投資スタイルで違ってくることです。基本的に7月までの上昇相場は米国の流動性に助けられたものでしたが、米国債の金利が高くなったことは流動性相場の前提が変わったということを示しますから、米国市場の基調が変化するまで再上昇は難しいでしょう。
2003年8月1日(金)
買い方は夏休みに適した場面。
来週の日経平均はレンジ内の動きを継続するか、下値模索となりそうで、買い方にとっては休みを取るのに適した時期でしょう。米国市場はいくつか予想を上回る経済指標がありながら昨日のマーケットは高値から落差のある水準で引け、高値更新したという力強さを示せずに引けていました。これは、既に相場水準の上昇でファンダメンタルズの改善を織り込んでいたことがあったからでしょう。
かなり意外性のある数字が出ない限り勢い良く上がらないのであれば、強気の投資家であっても押し目を待った方が得策と言えそうです。相場に参加していると、つい手を出してしまいますから「休むも相場」の格言が役に立つことになりそうです。
指数の動きと反対に、個別株はボラタイルな動きを見せるものが多く、それなりに興味深い相場です。業績による色分けが明確で素直な相場になり、株式市場の選別機能が上手く働いています。本来あるべき姿ですが、規制強化に思えた手口の非公開が良いほうに作用した可能性があります。
というのも、手口を追いかけて売買していた人たちが売買判断の拠り所を失い、株式本来の判断基準で売買せざるを得なくなったことが大きいようです。パッシブ運用全盛の時代で、アナリストには受難の時代でしたが、少し見直されてくるでしょう。格上げ情報なども以前より影響度が増しているようですし、投資態度においても個別の企業業績を良く調べるという基本が見直されてくると考えています。
その意味で年金基金の売買は株式市場に邪魔なものです。手口非公開で個人投資家は手口を気にすることなく良い銘柄の押し目をしっかり買えますが、公的年金は良いものも悪いものも同じ様にしか買えないという欠陥が指摘されそうです。運用担当者は果たして予期せぬ状況に対応するのでしょうか。
2003年7月31日(木)
円安は売り材料。
輸出企業にとって円安は勿論よいことに違いありませんが、株式市場にとって必ずしも良いことではありません。今回の上昇相場が「流動性相場」と言われるのは円高に対する今年5月の強力な介入から米国に多額の流動性を供給し、金利低下につながったことがあったからです。自然に円安となれば米国への流動性供給も止まるので、株式市場のミニバブルにもブレーキがかかりかねません。
また、外国人投資家がアセット・アロケーションを考える時、通貨の弱い国の債券や株式を買い増すことは出来ず、逆に売りが増えることがあります。今程度の円安ならそれほど大きな変化になりませんが、円安トレンドが出ているような場合に日本株を買い越した例はほとんどありません。日本にとって、円安は好悪両面ありますが、株式市場にとって円安はむしろ売り材料と言えるでしょう。
日経平均はボラタイルではあるものの、引き続きレンジ内の取引と見ています。TOPIX先物が売られており、大口の機関投資家の売りが続いていることを連想させます。出来高が減少し先物の存在感が増していることに注意が必要でしょう。今年になって月初のマイナスが一度も無いジンクスがどうなるかも明日の見どころです。
2003年7月30日(水)
機関投資家の「タンス株」処分を「個人年金」で買う。
日経平均は急反落しましたが、このところ株価の上昇に比べてファンダメンタルズの改善が追いついていない銘柄が多かったので、メッキが剥げ、需給がファンダメンタルズに勝てなかっただけのことでしょう。
悪材料を待って売り崩すタイミングを待っていた筋もあるようで、明日も継続するかもしれません。サイコロが6勝6敗に近い展開では上がれば強気、下がれば弱気が強調され、損の繰り返しになることが多いので注意が必要です。レンジ内の動きと見ていますが、米国がこれまでの反動で下げ始める可能性も考えておくべきでしょう。
ところで、本日も連れ安していますが、上昇過程においてトヨタや武田といった日本を代表するような優良企業の株価のパフォーマンスは大きく見劣りしたままです。上がらない理由は代行返上売りや持合解消売りと見られますが、これは機関投資家が売買する目的でなく長期保有していたものを処分する売りであり、個人のタンス株券の売りとどこか似ています。
目先の売買の投資家(投機家)は別として、法人の「タンス株売り」のひとつの山場は中間決算までですから、個人としてはゼロ%に近い国債など買わずに日本を代表する優良銘柄を長期保有の目的で買ってみてはどうでしょうか。長期保有なら昨日書きました松下電器も良いでしょう。
例えば、トヨタは環境問題の対応が世界トップレベルで、武田は1兆円を超える流動性の資産を持っていますし、松下電器はデジタル家電で世界的に強いといった特徴があります。これらのブルーチップを買うことは機関投資家の売りを「個人年金」としてポートフォリオに組むようなものです。長期投資なら世界的な競争に耐えられる銘柄を選ぶべきでしょう。
株式市場の優れた機能は選別機能ですから、個人投資家はどこかの閣僚の真似をしてETFを買うことはありません。良いものを選んで買って頂きたいものです。
特に、企業年金の売り(代行返上売り)は、今後も代行返上売りが残るものの、10月以降は返上された資金の6割程度が再投資されると言われており、これまでのように売り一辺倒から買う資金にまわる点が異なります。パッシブ運用で再配分するなら、トヨタが時価総額2位、武田が7位、松下電器が12位(6月末時点)といった点も逆に強味になってくるでしょう。
2003年7月29日(火)
松下の底力。
松下電器産業が5連騰と元気です。4月には860円まで売られていましたので、投資家の企業に対する評価は如何に変わり易いものか良く分かります。目先は4半期決算発表に対する期待で買われているのですが、デジタル家電に対する総合力が外国人投資家に認められてきた結果と言えるでしょう。
また、企業の持つ底力、長期にわたって築き上げた実力も見逃せません。大手電機会社のほぼ全社と取引しているある部品メーカーによると、「部品の返品率」は松下がトップだそうです。出す側の検査で合格したものでも30%も返品してくることがあるそうです。しかし、全く同じ部品でも他社はほとんど返品してこないところもあると言いますから、検査の甘い会社で作った製品と検査の厳しい会社の製品の信頼性の差は大きくなるに違いありません。
どんな部品でも採用してしまう会社の名前を公表する訳にいきませんが、良い会社は褒めるべきでしょう。そして、企業の底力というのは単に目先の数字だけでなく、長期に築き上げられた製品の信頼性が大きな要素です。
マーケットには再生機構扱いのボロ株を買うような参加者もいれば中長期のインベスターもいます。トヨタや武田のようなブルーチップが指数のパフォーマンスに負けていますが、中長期の投資家は優良銘柄を買うチャンスが来ているのではないでしょうか。りそなを買った方がトヨタを買うよりリターンが良かったというのは何かおかしいと松下の株価が主張しているようです。
日経平均は米国次第とはいえ、しばらく、本日の9950円高値と先週の9410円安値のレンジ相場入りした感があります。仮に、高値を更新したとしても売買金額が少なく、続かないと見ています。
2003年7月28日(月)
ピンと来ない日本の「2大政党制」
デフレに合わせた構造改革をすべきところを、小泉氏が「構造改革なくして成長なし」というスローガンを掲げ、規制緩和の無い郵政「改革」や独立性の無い大学の「独立行政法人」化など、間違った政策を連発したように思います。本当に構造改革を進めれば成長を止めることは明らかですから、出発点から躓いていたと言えるでしょう。
そこで、看板と中身が違う為に希望が持てない選挙民に対して、野党2党が合流して政権交代を目指すということになり、閉塞感のある日本を変える可能性を醸し出しています。しかし、選挙の前だけに、結果優先の合流では何かしっくりこないものを感じる方も多いことでしょう。
急な「2大政党」作りにピンと来ない理由はやるべき順序が逆だからでしょう。つまり、もともと2大政党制に近い状態があって選挙制度を小選挙区制に変えれば良かったのですが、ベースが無いままに決まりだけ変えてしまったので、数合わせの野党勢力を作ることになりました。そして、その状態を選挙民が見てきたから、再びその延長線上に今回の合流が追加されただけという醒めた見方が払拭できないということです。
既に、日本株は外国人投資家が主力であり、外からの視線で政権交代が可能な状況が作られていると見られれば更に評価が高まるかもしれませんが、今のところ野党の合流も日本独自の評価を与えられず、結果として、米国の写真相場を抜け出すところまで行かないと見るべきでしょう。
さて、日経平均は再び堅調さを取り戻していますが、株式相場以上に堅調さを取り戻しているのが債券市場です。暴落を演じた債券相場も今月4日以降はたいへん順調に上昇しています。債券市場が順調ということは裏返せば企業の資金ニーズがそれだけ伸びていないことを示し、債券売買のプレーヤーは相変わらずデフレの見方を変更していないことになります。
結局、どちらかの見方が間違っているのですが、「需給はファンダメンタルズに勝てない」ので何れ修正されることになるでしょう。但し、「目先は需給が優先」しますので、上値があってもおかしくありません。ひとつの指標と言えるソフトバンクが持ち合い圏を出しつつあるようで、全体にも影響を与えそうです。
2003年7月25日(金)
誘惑に負けると損をし易い状況。
方向感の出ない相場展開でしたが、このような時期に大相場の余韻で「ちょっと稼いでみよう」と軽い気持ちで参加すると失敗しやすいものです。市場参加者は相場が上がり始めると大相場の余韻がある為に(実際はそれ程魅力的な市場で無いにもかかわらず)どうしても参加したい気持ちを抑えることが出来ません。このような局面では、結局、「勝ったり負けたり」で成果は乏しくなるもので、相場と戦うより誘惑と戦うことが重要かもしれません。
米国の6月のSQ以降はそれまでの上昇パターンから明らかに変化しています。米国の信用売り残の大幅減少に示されるように、SQまでに売り方が手痛く敗退した結果、ショートカバーが減り、新規の買いだけで相場を上昇させることになり、力不足になったことが原因のひとつと見ています。
もうひとつ、大きな背景はそれまでの円高傾向が沈静化したことがあります。多くの市場関係者が指摘する様に、5月の円高局面で大量の覆面介入を行い、その後、ドルで運用し、米国債の金利を下げる流動性の供給となったことが株高の背景です。これが、このところの円安、ないし、為替の安定で介入資金が減少し、米国金利の反転上昇にもつながったのではないでしょうか。その分、債券市場から株式買いの資金がシフトしていないと思われます。
日経平均は再び為替や債券市場も含めて大きな流れが生じるまで待つべきところで、小幅な変動で凌ぐかどうか、あるいは、小さな変動の可能性が高いところでリスクを取ることが現実的に見合うかどうか見極めるべき場面でしょう。
2003年7月24日(木)
不思議と3・9月に偏る公的年金の買い。
年金基金が昨年度の公的年金の株式買いの実態について公表しました。その中で、当初買い予定の1.5倍の金額の株式を買った理由について、『株価が予想以上に下落し、資産の配分割合を一定に保つ為に(株式を)買い増した。』としています。従来からの方針説明通り、指数が安い時に公的年金は債券とのバランスを保つ為に株式を多く買ったと報告されています。
逆に、株高場面で、株式が一定比率以上になれば、公的年金の売りが相場を抑えることもありそうです。個人投資家にとって、日本株のボラティリティを低下させる邪魔者かもしれませんし、証券会社にとっても株式のダイナミズムを失わせてしまうことを考えると経営的にもマイナスの筈です。公的年金の動きに対して証券関係者から批判が少ないのは困ったことです。
それ以上に問題は、公的年金が『資産の配分割合を一定に保つ為に(株式を)買い増した』としながら、実際は、3月と9月に極端に配分が偏っている点です。例えば、2002年の9月は4326億円も買い越ししていますが、9月より相場が下がった10月は2486億円しか買っていません。9月に株価を支えるような配分をした反動で10月に多く買えずに下げてしまったと言えなくもありません。指数が安かった10月が9月よりも買っていない理由がはっきりしません。
また、今年の1月から3月は同じ様に株価水準が低かったにもかかわらず、1月は1420億円、2月は1434億円の買い越しとほぼ同額だったのが、3月になると急に3610億円の買い越しになっています。3月に2000億円以上も買いが増えた理由が分かりません。
ちなみに、3月19日の先物7770円の安値後、2日間で600円超の急騰場面があり、しきりに公的年金買いが噂されていました。その後、4月に相場低迷があったのは昨年10月と同様の需給悪化が関係していた可能性があります。果たして、運用責任者は3・9月に買いを集中させていることに関して、公的年金が本来の運用方針から離れて金融機関の決算のドレッシングに加担した疑いが無いと言い切れるのでしょうか。
日経平均はソニーの決算悪があり、3時過ぎに先物が急落した影響が明日に反映されそうです。ソニーが売られると値嵩の採用銘柄も連れ安する可能性があり、持ち合い相場を長引かせる結果になると見ています。
2003年7月23日(水)
銀行にも言い分がある。
銀行協会の三木会長が昨日の記者会見で金融行政に「反論」し、『繰り延べ税金資産の算入を制限するなら、他国のように繰越欠損の期間延長、税金還付、無税償却の3つがあってしかるべきだ。』と述べました。発言は全銀協会長の立場から、やや三菱東京の頭取の立場も感じられる内容ですが、銀行としては当然の言い分でしょう。
これまで、金融行政が不良債権処理の加速を言いながら税制はそれを妨げる方向で動いていた部分があり、行政の整合性の欠如が問題をこじらせていました。繰越欠損の期間延長や無税償却の範囲の拡大など、全企業に対してすぐにでも認めるべきでしょう。それによって、産業界のリストラが早まり、リストラが成功した企業は税金を払わずに済む分、設備投資を増やすことが出来ます。税制の影響は大きく、株式市場の短期売買の急増は税制変更の影響でしょう。ちょっとした変更で経済構造が大きく変わる可能性があります。
日経平均は「25日MAに接触後のリバウンド」という強い相場に欠かせないパターンで反発しており、かなり作為的な相場形成のようにも見えます。最近のピークがザラ場で25日MAから計ったように10%上方乖離で押し戻されていたことを合わせて考えると出来過ぎのようです。
まるで、指数が仕手化している印象ですが、上がり始めると追随する短期資金も多く、NECエレクトロニクスの上場で手控えられていた分、上値余地があるでしょう。それを戻り売りの機会にするべきかどうか見極める展開となりそうです。
2003年7月22日(火)
日本株の「カントリーリスク」
リスクと一口に言っても様々で、株式の保有者が通常「リスク」と考えているものは、株価が思惑通りにいかなかった時の「価格リスク」のことです。株式のリスクは「価格リスク」以外に企業が倒産するかもしれない「信用リスク」があり、板が少ないと思うように売買できない「執行リスク」もあります。売買高が減少すると執行リスクが気になります。
それに加えて、外国人投資家が主導している日本株の重要なリスクとして「カントリーリスク」があります。国内の個人投資家は日本のカントリーリスクについて、ほとんど考慮せずに売買していると思われますが、外国人投資家は全ての国にリスクを設定しつつ投資していますので、北朝鮮が核燃料の再処理を行ったというような行動に対して、日本株の買い増し姿勢を変化させるに足る要素になり得ます。
外国人の売買比率が低い時代には北朝鮮の問題に対して、日本は「消化難」として処理していましたが、外国人投資家が主導する市場ですから彼らがどのようなバイアスを持つのか気になるところです。今後、日本株に微妙な影を落とすと見ておいたほうが良さそうです。
さて、日経平均は引き続き調整局面にありますが、大きな下値もなく、買い辛い水準です。中途半端な水準で参加するより変化待ちで良いと思われます。ソフトバンク中心の材料株相場で、海外市場を反映した寄り付き以外では材料株が指数全体を動かすようなところがあります。
2003年7月18日(金)
降り時が肝心。
松井証券が公表している自社の顧客の信用評価損益率は昨日で売り方がマイナス11.42%、買い方がマイナス4.79%です。この数字は買い方のプラスのピークからは10%程悪化(売り方は改善)しています。
僅か1週間ほどで信用評価が様変わりですが、10%の変化はかなり大きく、強気も引くべきところで引かな買った場合、すぐにこれまでの利益を短期間で無くすことになります。
注意すべきは信用の評価がプラスの時は買い残が少なく、マイナス時のほうが信用の買い残が多いことです。いつもそうですが、「利益を出すときは玉が小さく、しこるときは玉が大きい」のが信用取引の全体像です。
これが起きる原因は心理学的にも証明できます。つまり、人間の満足や喜びを感じる中枢は、それが続くと、次に満足するレベルが上がってしまうので、より大きな金額を得なければ満足出来ない仕組みがあることが分かっています。いわゆる「慣れ」によるものです。
結局、最も強気を続けた投資家が下げ直前まで「英雄」であったものの、最後に最も大きくしこりを作り、動けないままに損のほうが大きくなるというのが何度も繰り返されたパターンです。その後、ファンダメンタルズが相場に追いついてくれば、買い方も報われるのですが、単にミニバブルであれば、相場の反動で逆に経済を悪化させる場合も有り得るのは昨日述べた通りです。
来週の日経平均は米国の調整局面を反映して、調整継続と見ています。これまでの上昇場面のアンワインドが進む場面でしょう。それでも、「根拠なき熱狂(?)」から醒めやらぬ参加者によって、時として、活況場面が再現されることもあり得ますので、売買のチャンスはまだ残されていると見ています。
2003年7月17日(木)
なぜ「空買い」規制は出さないのか?
今年の日経金融新聞のコラムで1番のお気に入りは11日の『「信用買い規制」なぜしない』のコラムです。コラムでは、『2002年3月に投機売りを見とがめて空売り規制を強化したのだから、今度は信用買い規制を導入すべきだ。』また、『購入代金が自己資金で無い場合は空買いの表示をし、上昇時に同値や上値の買いを禁止すれば良い。』というものです。公平な市場形成の観点から正論でしょう。
さらに、『株価の過度の下げが経済をおかしくするなら、過度の上げも同様だ。行き過ぎが修正されれば負債だけが残り、成長力がそがれることはバブルの崩壊が実証した。』とも述べています。
証券界や政治家は株価が上がるほど良いと信じきっているようですが、実際はそうではありません。株式市場の内部要因だけで考えても、信用取引の空買いは相場の高値ほど多くなり、下げると本日のように売買金額が8472億円と急減し、皆が売るに売れない状態になります。まさに、「行き過ぎは負債だけを残す」ことになります。
株価はファンダメンタルズを映す鏡ですから、ファンダメンタルズが株価の上昇に追いつけない状況で短期売買ばかり過熱していては経済にプラスの効果は知れたものです。過度の投機が問題なら、買いの信用規制をすべきですし、出来ないなら空売り規制を廃止すべきで、公平さを取り戻すか、自由な市場に戻すべきです。どちらも出来ないなら、金融政策は恣意的にしか運用できないと言われても仕方が無いでしょう。
日経平均は東証の大宴会終了後も熱狂から醒めやらぬ参加者によって下げ過ぎればある程度の反発は見込めると見ています。しかし、1兆円を超えるような売買が再び続かない限り調整期間が長引くこともありそうです。
2003年7月16日(水)
住宅ローンの返済困難が急増。
住宅公庫の発表では、返済が困難になり減額措置を受けた人が2002年に前年より77%も増加したそうです。問題はその増加率の凄まじさで、4年前から比較すると約10倍の人数です。2002年の完全失業者数は過去最高の384万人ですから、増え方が急である原因はリストラが主因であることは容易に想像がつきます。
しかし、それだけの原因かどうか疑問もあります。いくら不況と言っても4年で10倍に増加は多過ぎます。もしかすると、大手銀行の過大債務企業への債権放棄が個人のモラルハザードを引き起こした可能性はないのか気になります。真面目に返済する気持ちを無くした個人が増えてしまったかもしれません。日経の記事では「住宅ローンの延滞が銀行経営に重しになる」と述べていますが、モラルハザードを広げた責任は銀行にもあり、「身から出た錆」と言えなくも無いでしょう。
それにしても、最も働き盛りの日本人の40歳代は住宅ローンの借り入れを主体に全体で実質的な「債務超過状態」です。余裕のある個人は団塊世代であり、個人の株式投資が増えるべき働き盛りの世代で債務が大きく、期待できない状態にあります。
昨晩、グリーンスパン氏が議会で証言し、「日本経済はやや好転している」と述べた為に円高場面がありましたが、日本経済がドラスティックに好転することは構造的に難しいものがあります。
さて、日経平均は大相場後の休養場面とも、下げに転換したとも取れる展開ですが、大相場の余韻が大きい時は強気も弱気も偏るべきではありません。どちらの側でも振れが大きく失敗しやすくなるからです。下げ基調で戻り売りが有利と見ていますが、順張りは難しいのではないでしょうか。
ところで、日経新聞のコラム「まちかど」でドイツ証券のレポートにある1部昇格候補銘柄の具体名を取り上げていますが、ドイツ証券は前回も良く外した「実績」があり、結果はどうでしょうか。具体名を挙げたことで、2銘柄ともストップ高で買い物を残すほどの人気となったことは記者の「書き過ぎ」でしょう。この2銘柄、結果は勿論分かりませんが、思惑と異なり可能性は低いと見ています。記事による思い込みの「犠牲者」が出ないことを願うばかりです。
2003年7月15日(火)
大手銀行に「改善命令」、金融行政の責任は?
日経朝刊(14版)のトップで、金融庁は大手5行に業務改善命令を出すと報道しています。業績低迷で改善命令を出すのは初めてのことです。しかし、99年に公的資金を注入して以来、既に4年間、銀行の業績は低迷続きで、遅過ぎる対応と言えそうです。
銀行はいまだに数十歩も歩けば隣の店があるようなメガバンクが存在し、誰が見てもリストラに疑問があり、決算で債券の益出しで利益を水増ししているようなことでは改善の見通しが甘いと言われても仕方の無いことです。
これまで銀行のリストラが真剣に行われたとは言えないだけに、改善命令は当然のことですが、特殊法人の放漫経営と同様、監督官庁の責任は不問です。公的資金の注入で反対が多いのはその後の責任が曖昧だからで、りそなについても、誰も責任を取る必要の無いシステムにおいては何度やっても同じことになる恐れがあります。国が指導しながら2度破綻した兵銀の例もあります。
銀行はある意味で行政の指導のままに経営しているので、結果について後から責任だけ問われるのは銀行側にも言い分があることでしょう。問題は、これが強引な貸し出し金利の引き上げにつながったり、貸し渋りを引き起こしたりするようなデフレ促進策になる可能性もあり、この政策だけでは両刃の剣でもあります。借り手側にリストラの銀行員を受け入れさせるような圧力があれば企業も困るでしょう。
日経平均は相変わらず一方通行で、腰が座っていない売り方と熱の冷めていない買い方があり、上がり出すと瞬時に高値まで買ってしまうようなところがあります。一気に上値を取るのは無理で、中長期の参加者が少ないことを考えると、高値の揉み合いが精一杯では無いでしょうか。NY市場も同様な展開でしょう。
2003年7月14日(月)
ITバブルと擬似ITバブルの違い。
ITバブルが発生していた3、4年前と最近のIT銘柄の復活とを比較するとあまりに大きな違いがあり、今の状況が再びITバブルのようになる可能性はたいへん小さいように思えます。例えば、携帯電話の差は非常に大きく、当時のITブームでは加入者数の急激な増加で関連企業が量的に潤っていたことがありますが、今は「カメラの画素数の違い」を競うような付加的機能を争っており、機種変更ニーズで市場が保たれている感じです。
また、ITバブルには量的な拡大があり、拡大テンポが速かったことにより、将来の利益予想を大きく見積もれる「利点」がありました。その過大な見積もりがバブル的株価を正当化する理論的な裏付けとなったわけです。しかし、携帯電話の機能面を競っているようなITの進展において、株価が「バブル的暴走」をした場合、何を根拠にするのか明確になっていません。やはり、株価はファンダメンタルズを反映した水準に落ち着き所を探すことになるのでしょう。
ファンダメンタルズと言えば、証券株が下げ、率直な反応を見せています。指数が上昇しても、売買金額が減った為に、手数料収入に対する過度な期待が早速修正されています。証券会社の収益は振れが大きく、大商いの時を基準に業績を見通すことに元々無理があります。今後も、大商いが続けば売りのターゲットとして分かり易いグループとなるでしょう。
日経平均は米国の写真相場の度合いを強めていることから、どうしても海外企業の決算数字に一喜一憂の展開にならざるを得ません。今週は特に「大物」の決算発表が続き、結果次第で振り回されるリスクを考えるとポジションは取り辛いところです。
参加者全体にこうした手控え気分が強く、先週までと異なり、出来高減少と先物の存在感が増す状況であり、マニピュレーションの大玉の動きに注意すべきでしょう。どちらかと言えば、このところの米国は強気が優勢で、期待外れの業績に敏感に反応しそうです。個別では、仕手株物色ではなく、大商い時に無視されていた中小型銘柄の水準訂正が期待できそうです。
2003年7月11日(金)
「惰弱(だじゃく)な証券業界」と大手銀行。
日経金融新聞によるとサンリオの辻社長は40年も続けた株式運用をやめたことに対し、「取引金融機関は全て株式運用撤退を良いことだと口を揃えて言った。」そうです。サンリオの取引銀行は東京三菱、三井住友、みずほの大手銀行です。
大手銀行は揃って「株式運用は良くない」と言いながら、サンリオの持ち合い銀行株はそのまま持続で、それどころか、公募株の引き受けを要求したことは想像に難くないことです。日本のバンカーのレベルはこの程度のものでしょうか。
また、辻社長はどの証券会社からも『そんなことを言わないで株を続けよう』とか『資本主義経済だから株式投資は間違っていない』と言ってこなかったそうで、「いかに証券業界が惰弱であるかということだ。」と厳しく指摘しています。証券界もここまで言われれば少しは身に沁みてもらいたいものです。
日経平均は相場上昇の代表的銘柄であったソフトバンクがチャート上で買い方の大きなしこりを象徴する「離れ小島」型になったように、「急騰・急落」の高値波乱で上値のしこりが大きくなりました。来週は戻り売りの流れと見ています。東証の大宴会後に酔いが醒めない方々は要注意といったところです。
2003年7月10日(木)
株高に冷静な機関投資家。
今月4日に債券市場が大荒れになったのは、株式市場が想像以上に強くなった為に機関投資家も慌てたことがあったと思います。しかし、昨日の日経平均の急速な戻り場面と本日の高値更新場面では、機関投資家は全く冷静に債券を売るどころか買い進んでいました。
債券市場における機関投資家の主力は大手金融機関で、彼らは企業の資金ニーズの高まりを直に知る立場にあります。株高になびかず、超然と債券を買う姿は、余程、株高が示すほど設備投資や企業業績が回復しないことに自信を持っているのでしょう。彼らが正しいかどうかは後で分かることですが、少なくとも現場で資金ニーズの動向を知る彼らの行動を軽く見ることも危険でしょう。
日経平均は相場巧者も振り回されるようなボラタイルな展開ですが、明日のSQはオプションにしては空前の規模のSQが予想され、CSFBの出方次第で更に波乱も有り得ます。しかし、手口が分からず、混乱を増幅するかどうか初のケースだけに注目されます。混乱すれば短期売買のチャンスでしょう。全体的な印象では「東証の大宴会」が一旦峠を越した感じがします。
2003年7月9日(水)
仕手株になった?日経平均。
為替市場が平穏で債券市場もジリ高傾向と安定していた本日の相場で、2時過ぎから日経平均先物は仕手株と同様な値動きで高値引けとなりました。強気の買い方ですら、一旦利益を確定させ持ち玉を減らしていたような状況で、流れに逆行して大きなロットで先物を買い上がり、裁定買いを連続的に誘発させるやり方で、引け値に関与する仕手筋と同じで違反行為に近いものがあります。実際、いつもの「日本最大の仕手筋」が買い出動したという噂も出ていました。
このようなマニピュレーションは相場のリズムを崩すのが弊害で、日経平均も市場参加者が強気に傾いたところで梯子を外されることになるでしょう。ただ、高値警戒感が強い間は下げ難い状況です。建て玉の多いオプションのSQ直前に想定外の1万円が脅かされることで、またしても乱高下が起きそうです。
余談ですが、相場上昇に対するコメントで、証券会社の経営者や証券業協会のトップまでも「りそなへの公的資金注入をきっかけに相場が上昇した」と言っていることに閉口します。相場上昇はアジア各国のどの市場にも共通のことで、日本だけが特別に上昇したわけではありません。たぶん、公的資金を注入せずに破たん処理しても相場の上昇は変わらなかったと思われます。金融政策に追従的なコメントを流されると白けてしまいます。
株式市場の重要な機能は、努力して業績を向上させている企業を買い、駄目な会社を売る「選別機能」にあります。知る限り、証券会社のトップで唯一、松井証券の社長がりそなへの株主責任を取らない資本注入に否定的でした。金融庁のご機嫌を伺うような経営者が多い中で圧力を恐れない正論に敬意を表したいと思います。
たまたま、金融庁が東京海上に対し、朝日生命とのグループ化問題で別件で圧力をかけようとしたとされる問題があり、金融行政のあり方が国会で問題になっているところです。また、株式が上昇したことを行政手腕の成果と言わんばかりの大臣も、何も変わっていない中で、もう脇が甘くなったようです。
2003年7月8日(火)
ベンチマークに負けたのは機関投資家と仕手筋。
大商いでほぼ一本調子の上昇についていけない投資家が多いと察しますが、その中でも特に、成績が指数に追いつけず苦い思いをしているのは機関投資家と仕手筋でしょう。両極端の参加者が揃ってベンチマークに負けているのは面白い現象です。
機関投資家は株式の比重を落としていましたので、数%は指数に負けていると言われています。また、仕手筋にとっても面白く無い相場で、主力銘柄が軽々と仕手銘柄よりも派手に値を飛ばすので仕手株が用無しになっています。仕手筋は主力株が冴えない動きになれば復活することもあるでしょうが、機関投資家はここで株式の比率を上げても手遅れではないでしょうか。
また、金融機関にとっては今期も債券の売却益を多目に見積もっているところがあり、株式市場の上昇よりも保有高で3倍以上ある債券市場の下落の方が痛手になりかねません。ここで「株高」を阻止したいのは他ならぬ金融機関かもしれません。最近、日銀は銀行持ち株をあまり買わずに国債購入を増やす傾向にあり、どこまでも過保護な金融政策に見えます。
金融機関にとってファンダメンタルズの改善による株高であれば不良債権の減少で債券安は問題ありませんが、ファンダメンタルズと乖離して株高と金利高が進行する状況は困った問題です。好況でも無いのに貸出金利の引き上げが浸透する筈がないからです。
ナスダック高の影響でハイテク中心の上昇となり、日経平均は高値更新しましたが、株高ほど業績が向上していない会社が多く見受けられ、既に割高な株価まで買われている銘柄も散見されます。結局、需給はファンダメンタルズに勝てないので、日経平均はこれまでのような一本調子の上昇から異なる展開を見せ始める頃でしょう。
2003年7月7日(月)
ミニITバブル
個人投資家の主力は既にオンライン・トレーダーになり、対面営業ではありません。そして、オンライン・トレーダーで現在活躍中の個人は言わば、ITバブル崩壊後も「生き残ったつわもの」が多く、IT銘柄を再度相場の中心に担ぎ出したようです。本日はちょっとやり過ぎと思える程IT関連株が復活したのは「昔良い思いをした生き残り組」が年初から力を付けてきた結果ではないでしょうか。
また、個人のオンライン・トレーダーはこれまで売買手口からディーラーに裏をかかれることが多かったのですが、手口非公開でディーラーと「互角」になり、動き易くなったようです。手口非公開については個人投資家で反対する意見が大勢だったものの、実際は個人に有利に働いていることは間違いありません。規制強化と規制緩和の功罪は紙一重のようです。
ただ、この「ミニITバブル」が過去と異なる点は活躍銘柄が昔活躍した銘柄の「ネーム・バリュー」で担ぎ出された点と「値動きが良い」点に絞られていることでしょう。値動きの良いものに飛び乗り、上手く逃げれるかどうかの勝負といった感じです。とてもインベスターである機関投資家が付いていける相場とは思えません。
日経平均は先週の高値更新の可能性が出てきましたが、その場合、高値波乱をもう一度繰り返すこともありそうです。本日小幅な動きだった債券市場が株高の影響で崩れるようなことがあれば株先が買われ余計に上昇する可能性もあります。
2003年7月4日(金)
やはり選挙が近い?
総理大臣が持っている最高の権力はやはり国権の最高機関である国会に対する解散権でしょう。これを首相が一度も使わずに来年になるようでは任期満了選挙となりかねず、そのときの経済情勢に左右される選挙となり、うまくありません。
日経平均は昨年5月の高値と今年4月安値の中間である9842円を昨日のザラ場で達成し、いわゆる「半値戻し」となりました。選挙をする立場からすれば、4月頃と違って経済情勢、特に株価が足を引っ張る可能性が少なくなったことは重要な要素でしょう。
仮に、再び9000円以下に逆戻りすれば大手銀行の含み益が無くなる問題があり、かといって、株価を急上昇させると債券が暴落することも分かったので、微妙なコントロールが必要になってきました。出来れば「半値戻り」の水準を最低線の維持基準にしたいところでしょうが、債券市場に悪影響を与えるようなオーバーヒートを避けながら関与する必要がありそうです。「秋の総選挙」を前提とすると株式市場は「モラルハザード相場」が延長戦に入ることも視野に入れておくべきでしょう。
来週の日経平均は長期金利の急上昇を避ける為にも調整が必要で、仕手・材料株物色でつなぐ展開となりそうです。また、118円以下の円高局面になるとドル買いの介入が始まる可能性があり、流動性の供給につながる結果になります。
2003年7月3日(木)
市場の「物理的限界」と「執行リスク」
本日は1兆7154億円の売買金額に示されるように大商いで、各オンライン証券の注文がスムーズに出せない「恒例のトラブル」の他に、東証や大証までシステムに問題を生じたようです。取引所自体の許容量の限界が見えた感があります。これ以上活況になれば、参加者はいつトラブルに巻き込まれて注文が執行できなくなるかも知れず、「執行リスク」の重みに耐えなければなりません。
仮に、デイトレのつもりの商いでも、引け前にシステムダウンすれば、反対売買できずに米国の相場が自分に有利に動くことを願う他に打つ手が無くなります。特に、大証からの先物情報が取引があるにもかかわらず、引け前に途切れたことでオプション市場は正常な価格形成が出来なくなったことは問題です。
もし、売買出来なくなるようなトラブルが起きたとしても各証券会社や取引所がオーバーナイト・リスクを補償するとは思えないだけに、投資家の不可抗力による「自己責任」は取りようがありません。「今年のテーマは投機」と年初から述べましたように、これが毎日続くことは無いとしても投機的な短期売買の盛り上がりは今後も何度か起こり得ますので、対応を急いで頂きたいものです。
日経平均は市場が限界に達するような大商いの後だけに休養が必要で、調整気味に推移すると見ています。また、債券・為替市場などもたいへんボラタイルな展開で、他の市場と相互に影響し合うような荒っぽい場面の継続も考えられます。
本日が最近の相場において最も結果に差がつきそうな場面でしたが、今日の寄り付きでどのように行動したかが特に決定的だったと思います。特に、寄り付きから主力銘柄を大量に買った機関投資家は債券をゼロ金利近くで買いあさり、株式を急騰場面で買ったことになります。一体何を考えているのか呆れる方も多いことでしょう。
2003年7月2日(水)
実は過熱していない「投資家」
東証の出来高は銀行株などを千株単位に換算すると30億株近い出来高になり、出来高だけを見ると相当な過熱ぶりです。もし、これが対面営業だけの時代であれば営業マンに電話がつながらないといった物理的な限界があり、簡単に実現できなかったことですが、オンライン経由であればシステムが止まらない限り、注文はいくらでも増やすことが可能です。
また、ディーラーも取引所直結の端末から発注するので株価が動けば1日に何回でも注文を出し続けることが可能です。株式市場と構成が異なる為替市場では実需が10分の1以下と言われていますが、投資や輸出入などに伴う少ない実需の動きに大勢のトレーダーが資金を動かし実需に追随します。
ここ数日の東証は為替市場に近い売買になってきたようで、外国人投資家の手口が急増している訳でもなく、少ないインベスター(投資家)の動きにスペキュレーター(投機家)が群がっている構図ではないでしょうか。市場が過熱気味といっても短期売買の過熱であり、「投資家」は意外と冷静かもしれません。
問題は、短期売買目的の参加者がどの程度の玉をホールドしているかでしょう。個人にしても信用の評価損益がプラスになり、売り惜しみでホールド玉を多く持っている人もあるでしょう。上昇時は大商いですが下げ相場では出来高は急減しますので、潮目が変わる前に降りれるかどうか技術的な問題になりそうです。
日経平均はたぶんオプション取引史上で最高の建て玉数となる95コールが踏み上げ状態となり、この点からもオーバーシューティングになリ易い状態です。その機械的なリバランス買いもあり、高値波乱の可能性が一段と増したと見ています。とはいえ、現物株主導の相場であり、流動性相場のなかで出遅れ気味だった大手銀行株やNTTドコモなどの個別の大型銘柄の動きに指数が左右されそうです。
2003年7月1日(火)
ファンダメンタルズが読めない理由。
東証は大手銀行株が大商いで実質20億株を大きく上回る活況でした。売買金額も1兆円を超えています。このような中で、寄り前に発表された日銀短観は好悪両面があったものの、需給が良い日は悪い点を無視するもので、大企業のDI改善が買い手がかりになりました。需給が悪い時期には全く無視されたこともありましたから、様変わりの反応です。
もともと専門家でもファンダメンタルズを読むことは至難のことですが、参加者は自分のポジションの都合の良い部分ばかりを読みたがるので、結局、先が読めずに失敗することが多くなりがちです。「需給は目先の株価に影響し、ファンダメンタルズは将来の株価を決定する」と考えるとファンダメンタルズについて目先の株価動向で急に見通しを変えるべきではありません。
短観では「企業の売り上げが1.1%減少するのに経常利益が11.9%も伸びる」という矛盾した企業側の見通しがあり、これを実現する為には強力なリストラが必須で計画の甘さが気になります。また、各企業がリストラを進めるなら、相変わらず国内でリスク資産を持てる法人が少なく、資産デフレの圧力は依然かかったままです。増益が達成されても株価トレンドを変えるには全体のパイが大きくなる必要があるでしょう。
日経平均の水準は今年の高値を更新しましたが、NYのテロ事件当時の急落した株価よりまだ安く、ファンダメンタルズから説明し難い相場でも水準的に成立していると言えそうです。債券相場の軟調さも株高を支援し、相場に勢いがあることからもう少し上値を見ることが出来るでしょう。とはいえ、出来高に過熱感があり、売りでも取れる場面がありそうです。